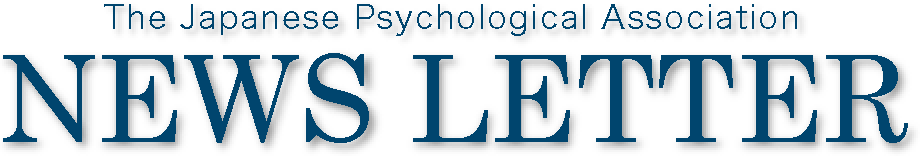

認定心理士の皆様、あけましておめでとうございます。
前回の新年のご挨拶は、学術大会が、コロナ禍の制限から解き放たれつつあることを話題にさせていただきました。感染自体はまだくすぶっているとはいえ、もはやコロナ禍は過去のものとなったように感じます。あの頃は、あんなに不自由したのに、もう、実感を伴って思い出すことすら難しくなってきました。
さて、2024年9月に開催された日本心理学会第88回大会は、一部、web配信や録画配信を併用しながら、熊本城ホールを会場に、対面で行われました。
会員交流会は、ポスター会場で盛大に行われ、「ポスター発表延長戦・前哨戦」が同時開催されました。自主的にポスターを貼ってくださった発表者を囲んで、飲食をしながら議論するという、新しい試みです。自主的発表者の方が飲食を十分にできなかったことが反省点ですが、今までにない、のびやかな学術交流が実現したと思います。
熊本城夜間貸切ツアーも実施しました。閉鎖後の熊本城を貸し切り、普段見ることのできない、天守閣からの夜景も堪能していただきました。予想を超える人気で、当初250名だった定員を350名まで増やして対応しました。アテンドさせていただいた海外からのお客様が、2016年4月の熊本地震から復興中の石垣を、真剣にご覧になっていたのが印象的でした。
この大会では、認定心理士の会運営委員会主催で、大会企画シンポジウム「災害と避難の心理学」が開催されました。多くの皆様にご参加いただき、充実したシンポジウムとなりました。認定心理士の会運営委員会が選定した「シチズン・サイコロジスト奨励賞」の表彰は、受賞者ご欠席のため、現地で表彰できなかったのが残念ですが、今後も、年次大会において、認定心理士の皆さんに有益なイベントを実施したいと考えています。
2025年の年次大会は、9月5~7日の3日間、仙台の東北学院大学を会場に実施される予定です。仙台市民の一人として、皆様のご来仙を楽しみにお待ちしています。
(日本心理学会理事長:阿部 恒之)
オンライン開催・対面開催いずれのイベントも、お住まいの地域にかかわらずお申込みできますので、ぜひ多くのイベントにご参加ください。
-
認定心理士の会関東支部は以下の要領で公開セミナーを行います。
- 2025年2月9日(日)13:00~16:30(開場12:30)
- 大妻女子大学千代田キャンパス本館F棟2階コタカフェ
- 矢澤 美香子先生(武蔵野大学)、生田目 光先生(筑波大学)、荻原 かおり先生(東京インターナショナルサイコセラピー・二子玉川オフィス)
- 現代社会は、外見について意識させるような刺激にあふれています。そのような社会において、自分の身体をネガティブに評価し、受容するのが難しいと感じる人も少なくないようです。しかし、自分の身体を受容することは、自分を好きになることにつながるため、とても大事なことといえます。そこで今回は、自分の身体を受容していくために役に立つ心理学の知識と手法について、ごく一部ではありますがご紹介したいと思います。
- 申込み受付期間は終了いたしました。
(関東支部:鈴木 公啓)
-
認定心理士の会中国・四国支部は以下の要領で公開セミナーを行います。
- 2025年3月1日(土)14:00~15:30(対面開場受付13:30~、オンライン受付13:50~)
- 県立広島大学広島キャンパス1175講義室(広島市南区宇品東1丁目1-71)およびZOOMオンライン会場
- 寺澤 孝文先生(岡山大学 学術研究院 教育学域)
- 日本の教育支援はどのように進化しているでしょうか。本講演では、心理学とビッグデータの融合が教育にもたらす歴史的転換を最新データからご紹介します。例えば、意欲を失った子の意欲を高めることを「保証」できるようになりました。5分程度の見流すような勉強が、英検等のスコアを上げられることがわかってきました。教師などがアンケートをしなくても、学校の子ども一人ひとりの意識変動が3週間単位で可視化できるようになり、自殺やいじめを予知することも将来的に可能になってきました。これまで教師に限られてきた教育支援を、多様な専門家が遠隔で担えるようになる教育支援の未来を描き出します。この機会に、心理学が切り拓く次世代の教育支援の姿を体感してください。心理学が果たす役割は間違いなく想像を超えるほど大きくなります。
- 2025年2月25日(火)
- 「認定心理士の会イベント」(https://psych.or.jp/authorization/ninteinokaievent/)より事前にお申込みください。
(中国・四国支部:向居 暁)
【北海道支部企画】認定心理士の会 公開講演会(対面開催)「「繊細さん」「HSPブーム」とは何だったのか?―ポピュラー心理学に対してある一人の心理学者が取り組んできたこと―」
北海道支部は、2024年10月20日(日)に「「繊細さん」「HSPブーム」とは何だったのか? ポピュラー心理学に対してある一人の心理学者が取り組んできたこと」と題した一般の方にも公開した講演会を対面で開催しました。ご講演者は、飯村周平先生(創価大学教育学部)でした。当日は71名(うち認定心理士13名)にご参加いただきました。
飯村先生の講演は、High Sensitivity Person (HSP)という概念がブームとなったことで、生きづらさや傷つきやすさを抱える人々や現代社会にどのような影響を及ぼしたかについて、実際に先生が行われてきた研究活動を基に紹介していただきました。特に、HSPをよりよく理解するためには、HSPか非HSPかで分けるのではなく、環境に対する個々人の感受性の違いに目を向けることが重要であるとお話いただきました。またHSPという言葉が多くの人々に浸透したことから、誤情報やそれによる弊害に対して行ってきた取り組みについてお話いただきました。
末筆ながら、講師の飯村先生をはじめ、本講演にお力添えいただいたすべての皆様に厚くお礼申し上げます。
(北海道支部:西郷 達雄)
【東北支部企画】認定心理士の会 特別講演(対面開催)「村瀬嘉代子先生に伺う心理学の過去・現在・未来」認定心理士の会 特別シンポジウム(対面開催)「近年の犯罪被害者等支援制度を踏まえた専門職協働の在り方~京都アニメーション事件被害者、弁護士及び公認心理師の視点からの検討~」
2024年8月27日(火)15時より宮城学院女子大学ハンセン記念ホールにて、東北心理学会第77回大会との共催の特別講演「村瀬嘉代子先生に伺う心理学の現在・過去・未来」を村瀬嘉代子先生(大正大学)と大橋智樹先生(宮城学院女子大学)との対談の形で開催いたしました。村瀬先生は幼少期の体験や家裁調査官としての経験を交えながら、自分の身体的な特徴、家族の背景などの本人の責任ではないことで「発達障害」といったラベル付けをすることへの問題意識を提起され、その人自身を尊重して支援していく重要性を強調されました。また、自分が生きることは相手も生きることと述べられ、相手に歩み寄り、互いに分かり合うことの必要性を強調されるとともに、自らの努力を通じて初めて質のよい誠実さを得られるといったお話もありました。村瀬先生が語られた経験と考察は、心理学を学ぶ多くのものにとって重要な示唆を含むものであり、本講演は心理学の未来を見据えた貴重な学びの機会となりました。
また、8月28日(水)13時より同会場にて、同大会との共催の特別シンポジウム「近年の犯罪被害者等支援制度を踏まえた専門職協働の在り方」を開催いたしました。本シンポジウムでは、京都アニメーション事件被害者であるA氏、弁護士である大張慎悟氏(大張法律事務所)、公認心理師である小澤優璃氏(宮城県警察犯罪被害者支援室)がそれぞれの立場から支援の在り方を共有しました。犯罪被害者にとって心理職は安全基地となり、心理教育や回復力支援を提供する重要な役割を果たす一方で、弁護士は被害者の権利を守り、状況の理解を深め、二次被害を防ぐ支援を行うというお話がありました。また、裁判における被害者参加は、内的な意見を社会に表明することで、被害者が生きる力を得るプロセスとなるというお話もありました。本シンポジウムでは、専門職と被害者の視点から新たな支援の道筋を見出す意義深い議論が展開されました。
(東北支部:河地 庸介)
【関東支部企画】認定心理士の会 公開セミナー(対面開催)「ワーク・エンゲイジメントとリーダーシップの最前線―理論と実践から考えるこれからの人材育成―」
関東支部のイベントとして、2024年7月13日(土)の14:00~17:00に公開セミナー「ワーク・エンゲイジメントとリーダーシップの最前線-理論と実践から考えるこれからの人材育成-」を開催しました。事前申し込みの上での対面開催となりました。事前申し込みは152名、当日参加は100名(うち認定心理士有資格者57名)と、参加人数も多く、本テーマに興味や関心が強い方々に参加頂くことができました。
今回は、ワーク・エンゲイジメントとリーダーシップをテーマとしていました。近年の日本では、働き方改革のもと、職場の魅力を高め、従業員の満足度・生産性の向上や人材不足への解消への取組みが求められています。一方で、日本の職場でエンゲイジメントが高い従業員がほとんどいないことが指摘されており、改善が必要であると考えられます。いくつもの研究においてリーダーシップがワーク・エンゲイジメントを高めることが実証されており、リーダーシップのあり方もまた、働く方の健康増進と仕事のパフォーマンス向上にとって重要な概念だと考えられます。今の日本において求められるリーダーシップとはどのようなもので、ワーク・エンゲイジメントを高めていくための取組みにはどんなものがあるのかは重要なテーマだと言えます。
登壇されたのは、島津明人先生(慶應義塾大学)、池田浩先生(九州大学)、江尻祐子様(日本航空株式会社 人財本部)のお三方でした。島津先生からは、「ワーク・エンゲイジメント:健康で活き活きと働くために」というタイトルでワーク・エンゲイジメントの概念や近年の動向についてお話し頂きました。池田先生からは、「リーダーシップ論のパラダイムシフト」というタイトルでリーダーシップ論の歴史的な変遷についてお話し頂きました。江尻様からは「ワーク・エンゲイジメント向上を支える現場のリーダーシップ」というタイトルで現場において実践されている事例や課題についてお話頂きました。
事後のアンケートでは、興味深く、現在の仕事に役立つ内容であったなど、参加者に非常に満足頂いたことが伺えました。今後も、現場や日常生活への実践に有用なテーマについて企画していきたいと考えています。
(関東支部:本田 周二)
【東海支部企画】認定心理士の会 公開シンポジウム(オンライン開催)「働き方の心理学」
2024年8月3日(土)の14時よりオンライン(Zoomウェビナー)にて、「働き方の心理学」というテーマで東海支部の公開シンポジウムを開催しました(事前申込制、無料)。本イベントの参加者は303名(関係者含む)でした。筑波大学の尾野裕美先生と文教大学の正木澄江先生にご講演いただきました。
尾野先生からは「育休を取得した男性の心理と働き方」というタイトルでお話をいただきました。民間企業において1ヶ月以上の育休を取得した複数名の男性へのインタビューから、育休取得者の内的な変容プロセス及びその影響要因をモデル化したご研究の成果を中心にご紹介いただきました。正木先生からは「人は働くことをどのように意味づけていくのか」というタイトルでお話をいただきました。働くことの意味づけに関する諸理論をご紹介いただいたうえで、民間企業に10年以上勤務する正社員を対象としたインタビューから働くことの意味づけプロセスモデルを生成されたご研究や、質問紙調査による量的な検討、縦断的な検討の成果についてお示しいただきました。
質疑も大変に盛り上がり、育休をとる人だけでなくそれを支える人への支援のあり方や、家事を含めた上での働く意味の捉え方など、幅広い観点からの議論が展開されました。アンケートでは、「なんとなく曖昧にしていたことを言語化して頂いた内容で、非常に勉強になりました」「わかりやすく丁寧なお話をありがとうございました」「自分自身にも、また働く人のためにも役だつセミナーでとても良かったです」「ご講演のみならずQ&Aを多くとっていただき理解を深めることができました」など、多くの好意的な感想を頂戴いたしました。
余談ではございますが、当日は全国的に天気に恵まれたものの、東海地方では名古屋市の最高気温が38.4℃と、酷暑となった一日でした。対面で開催していたら、熱中症の危険もありますし、これほど多くの皆様にお集まりいただくことは難しかったかもしれません。オンラインでの交流の機会を当たり前のように持てるようになったことも、働く環境の大きな変化の一つと言えそうです。そうしたオンラインの利便性も実感しつつ、働くことの意味について多角的に考える機会を持てましたことを大変嬉しく思います。
貴重なお話をいただきました尾野先生、正木先生、支えていただきましたスタッフの皆様、そしてご参加いただきました皆様に心より感謝申し上げます。
(東海支部:吉田 琢哉)
【北陸支部企画】認定心理士の会 公開講演会(対面開催)「いま、基礎心理学の教育と研究を考える」
2024年12月14日(土)に、北陸心理学会の年次大会内において、北陸支部との共催企画として「いま、基礎心理学の教育と研究を考える」を開催しました。北陸支部運営委員の森本 (仁愛大学)によるあいさつと谷内通先生(金沢大学)からの企画趣旨の説明に続いて、荒木友希子先生(金沢大学)の司会のもと、伊丸岡俊秀先生(金沢工業大学)、土屋めぐみ先生(いなだクリニック)、樫村美智子先生(公立能登総合病院)、荒木(玉居子)暢通先生(石川県七尾児童相談所)、石川健介先生(金沢工業大学)より、それぞれお話いただきました。
ご登壇いただいた先生方のご所属は、大学という教育機関や心理実践の最前線など多様でしたが、それぞれの環境で自らが受けてこられた基礎心理学の教育が役に立っていることはもちろんのこと、他業種の方との交わりの中で周囲から指摘を受ける形などで、それが自分の仕事の中で活かされていることを改めて実感することがある、というお話が印象的でした。公認心理師養成カリキュラムにおいて、基礎心理学が重要な位置づけにされていることは確かでしょうが、職業として心理学を活かす形を目指す中では、多様な心理学に触れる必要性がどうしてもあり、以前と比べて教育全体が「浅く平板になっている」感覚は現場にもあると思います。しかしながら、心理臨床の実践現場など、心理学の学びが直接・間接的に活かされる職種についた際に、学びなおしが必要になった時には、基礎心理学にしっかりと「深く」触れていた経験が、今に役立っているというお話は、フロアの聴衆も含めて深くうなずけるものでした。私も基礎心理学の教育に携わる身として、改めて基礎心理学の有用性について、現在進行形で心理学を学んでいる人にはもちろんのこと、それ以外の人にも、学問としての基礎心理学に触れる機会が増えるように、今後の認定心理士の会企画なども考えていこうと思いました。
今後も北陸支部は、北陸の心理学研究や教育を皆様に紹介する機会と、認定心理士の皆様の相互交流の機会を企画していきます。
(北陸支部:森本 文人)
【近畿支部企画】認定心理士の会 公開講演会(対面開催)「生成AIと心理学」
近畿支部のイベントとして、公開講演会を11月30日(土)に対面形式で、京都橘大学にて開催いたしました。講演会には13名(うち認定心理士9名)の方が参加されました。
生成AIの登場は社会に大きなインパクトを与え、私たちは何らかの形で生成AIを利用することが増えています。例えば、芥川賞を受賞した作品を書かれた九段氏は生成AIを利用したことを明らかにしていますし、生成AIを用いたツールを導入している企業も複数存在しています。教育や研究においても同様です。多くの大学はレポート作成などにおける生成AI利用に関するガイドラインを学生に示していますし、生成AIを用いた研究も増えています。報告者も日々の教育・研究活動に生成AIを用いるようになりました。
その一方で、生成AI利用に関する問題も指摘されています。著作権の問題はよく耳目にするところですし、教育面で言えば、いわゆる「丸投げ」はよく言われています。
そこで本講演会では生成AIを利用した教育・研究に関して造詣が深い浦田悠先生(大阪大学全学教育推進機構准教授)にご講演いただくこととしました。
講演では、まず生成AIの特徴として、テキスト、画像、音声、動画など、様々な種類のコンテンツを生成できることが紹介されました。また、生成AIの利点として、作業効率化、アイデア生成、情報収集、相談相手としての活用などが挙げられました。次に、高等教育における生成AIの課題として、学問的誠実性の問題、プライバシーとセキュリティの問題、誤った出力の問題、AIへの過度な依存の問題などが指摘されました。特に、学生が生成AIを使用してレポートを作成する場合の剽窃や不正利用のリスク、また、生成AIが出力する情報が必ずしも正確ではない可能性(いわゆる「ハルシネーション」等)について注意喚起がありました。
さらに、心理学教育における生成AIの活用可能性について、具体的な例を交えながら説明がありました。例えば、シラバス案の作成、ワーク案の設計、資料用イラストの作成、試験問題案の作成、学生へのメール文面案の作成などが挙げられました。
最後に、心理学研究における生成AI活用についても触れられ、ConsensusやSciSpaceなどのツールの紹介、ツールを用いることでの今後の研究の進展に期待が寄せられました。
浦田先生のご講演は、生成AI技術の発展が心理学にもたらす可能性と課題を理解する上で非常に有益でした。特に、生成AIを教育や研究に活用する際の注意点や倫理的な問題について詳しく解説いただき、今後の自身の活動においても参考にすべき点が多くありました。
(近畿支部:岸 太一)
【九州・沖縄支部企画】認定心理士の会 公開セミナー(オンライン開催)「現代にこそ大事な学びとは―教育心理学の観点から―」
2024年9月28日(土)の13時から16時まで、「現代にこそ大事な学びとは ―教育心理学の観点から―」と題して、認定心理士の会 九州・沖縄支部による2024年度公開シンポジウムが開催されました。会場はZOOMオンライン会場で、当日の開催の挨拶および司会進行は、本企画を担当した一人である中村学園大学の三上が行いました。当日の参加者は193名で、認定心理士の方は138名でした。話題提供の先生方は、教育心理学について研究をされている3名の先生でした。概略とまとめは、当日の講演順に以下の通りとなります。
最初に、福岡教育大学の生田淳一先生からは、「自ら問うことの価値」というタイトルで、学習者が質問をするのはどういったときか、どのようにして質問するのか、また、質問は学びにつながることを、事例やご本人の研究成果を踏まえながらお話いただきました。
次に、中村学園大学の野上俊一先生からは、「知りたい気持ち」というタイトルで、知りたい(知的好奇心)気持ちを増やすには、学習者本人が知りたい気持ちを持つだけではなく、その気持ちが引き起こされるような場面にも着目する必要があることを、ご本人の研究成果を踏まえながらお話いただきました。
最後に、宮崎大学の尾之上高哉先生からは、「学習内容の定着を図るために」というタイトルで、学習内容の定着を図るということは、学習者が学習内容を理解、記憶し、必要な時に適切に使用できるようにすること、また、学習内容の定着を図るための方法の1つとして、練習をして定着をさせる、との解説をもとに、ご自身の研究の成果を踏まえながらお話いただきました。
今回のシンポジウムは、話題提供の3名の先生方ならびに多くの認定心理士の方にサポートをいただきました。また、認定心理士の会運営委員であるNECソリューションイノベータの宮島健先生には、企画から当日の司会進行まで幾度となくお力添えいただきました。末筆ながら、今回のシンポジウムに携わっていただいた全ての皆様に心から御礼申し上げます。
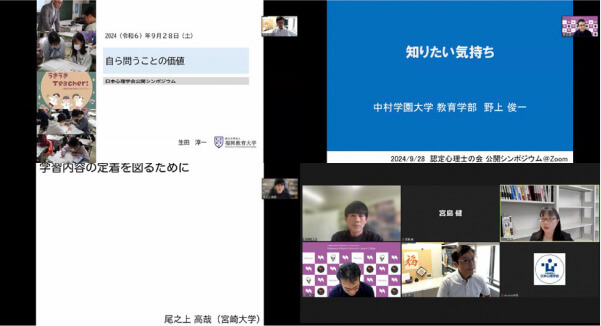
(九州・沖縄支部:三上 聡美)
【九州・沖縄支部企画】認定心理士の会 公開講座(対面開催)「九州心理学会 第85回大会公開講座」
2024年12月21日(土)の13:15から14:45まで、西南学院大学で開催された九州心理学会第85回大会において、「マインドフルネスという古くて新しい心の在り方:やわらかく、強く、やさしい在り方」「災害時の心理的支援」「気楽に高めよう再現性」の3つの公開講座が行われました。当日の参加者は計78名で、認定心理士の方は15名でした。話題提供の先生方は、九州(福岡県)において心理学の教育や研究、実践活動に取り組まれている3名の先生でした。概略とまとめは以下の通りです。
最初に、福岡県立大学の小山憲一郎先生からは、「マインドフルネスという古くて新しい心の在り方:やわらかく、強く、やさしい在り方」というタイトルで、ストレスマネジメントプログラムの一環としてマインドフルネスに注目し、自身が研究・実践している肥満症の治療(ダイエット)のマインドフルネスの利用についてご紹介いただきました。
次に、九州大学の野村れいか先生からは、「災害時の心理的支援」というタイトルで、災害のような非常事態での支援に心理職として何ができるのか(できないのか)、有事に備えて普段の業務で自分にできることは何かを考える契機と同時に、災害時のメンタルヘルスやソーシャルサポートについてお話しいただきました。
最後に、九州大学の山田祐樹先生からは、「気楽に高めよう再現性」というタイトルで、世界的な注目が集まった「再現性の危機」に焦点を当て、ご自身の研究の成果を踏まえながら、研究成果の発信者・受信者の両方の立場から再現性とどう向き合っていくかをお話しいただきました。
今回のシンポジウムは、話題提供の3名の先生方ならびに多くの認定心理士の方にサポートをいただきました。また、九州心理学会事務局である久留米大学の原口雅浩先生には、企画から当日の司会進行まで幾度となくお力添えいただきました。末筆ながら、今回のシンポジウムに携わっていただいた全ての皆様に心から御礼申し上げます。

(九州・沖縄支部:宮島 健)
-
- 2025年2月16日(日)14:00~15:00
- ZOOMオンライン会場(定員500名・参加費無料・入退室自由)
- 猪原 敬介先生(北里大学)
- 読書は良いものだと言われるけれど、実際の効果はどんなもの?過大評価も過小評価もせずありのままの「読書の力」を見つめ、その力をうまく利用する方法を探ります。
- 2025年2月11日(火)
- 日本心理学会ホームページでご案内しています。https://psych.or.jp/authorization/ninteinokai-book_20250216_dokusyo/
(新刊連動講座WG長:河原 純一郎)
【認定心理士の会運営委員会企画】日本心理学会第88回大会大会企画シンポジウム(対面開催)「災害と避難の心理学」
日本心理学会第88回大会企画シンポジウムとして、令和6年9月8日(日、大会3日目)に、「災害と避難の心理学」を対面開催しました。企画代表は日本心理学会認定心理士の会運営委員会でした。 話題提供者とタイトルは、邑本俊亮先生(東北大学)「防災教育への心理学からのアプローチ」、前田楓先生(立教大学)「親子間データから考える防災教育の可能性」、矢島潤平先生(別府大学)「熊本・大分地震における心理支援の実践」でした。
企画趣旨は地震や水害、土砂崩れなどの災害に、心理学の知識や技術はどのように貢献できるかを問うことでした。平成28年(2016年)の熊本地震、平成30年(2018年)の北海道胆振東部地震、令和6年(2024年)の能登半島地震など、平成23年(2011年)の東北地方太平洋沖地震の後にも大きな地震災害は続いています。予測しにくく、生活や人生に深刻な影響をもたらしうるこれらの事態に、対応し、準備するために心理学の知識や技術はどのように活かされているかを、この3名の専門家から伺いました。
冒頭にまず、邑本先生からは一般向けの防災講話の中に心理学的知識を組み込んだ実践例を伺いました。次に、前田先生からは、大学生とその親を対象とする実験事例や、より実践的な防災教育のあり方についてご紹介いただきました。矢島先生からは熊本・大分地震における被災者支援活動、支援者支援及びロジスティクス業務についての実践事例紹介と災害支援の課題と展望についてお話いただきました。最後に再び邑本先生から、小中学生を対象とした防災出前授業の効果測定の研究例、今後の防災教育の一形態として「学び手が伝え手になる震災伝承」の実践事例についてご報告を頂きました。第2会場は大きな部屋でしたが、日本心理学会会員、認定心理士の会会員、一般の方々の参加があり(95名)、活発な質疑応答がありました。話題提供の先生方、ならびに会場にお越し下さった皆様にお礼申し上げます。
(運営委員会委員長:河原 純一郎)
【認定心理士の会運営委員会企画】2024年度第4回新刊連動講座認定心理士の会×かもがわ出版『モチベーションの社会心理学』刊行記念イベント「『やる気』の理論を具体例から学ぶ」
2024年10月6日(日)に実施しました。講師は竹橋 洋毅先生(奈良女子大学)、参加者は188名(うち認定心理士151名)でした。
【認定心理士の会運営委員会企画】2024年度第5回新刊連動講座認定心理士の会×金子書房『心理学における構成概念を見つめ直す』刊行記念イベント
2024年11月9日(土)に実施しました。講師は仲嶺 真先生(公益社団法人国際経済労働研究所)、参加者は105名(うち認定心理士64名)でした。
【認定心理士の会運営委員会企画】2024年度第6回新刊連動講座認定心理士の会×福村出版『血液型性格心理学大全』刊行記念イベント「血液型性格と心理学―血液型と性格は本当に関係があるのか?歴史とデータから明らかにする―」
2025年1月25日(土)に実施しました。講師は山岡 重行先生(聖徳大学)、コメンテーターは渡邊 芳之先生(帯広畜産大学)、 参加者は214名(うち認定心理士168名)でした。
(新刊連動講座WG長:河原 純一郎)
初めてのニューズレターの編集作業が、大学共通テストと重なりました。試験監督は大学教員にとって大切な役割のひとつです。幸い何事もなく時間が流れる中、マインドがワンダリングし始めます。その行き着く先は、「編集後記に何を書こう…」。視界に広がる受験生たちの間を思考が彷徨います。鉛筆がカラカラコロリ――。その音色に心が引き戻されると同時に、受験生の真剣な表情に意識が合わさります。いかんいかん。
2月には大学入試が本格化します。「頑張れ、受験生!」――そして、「がんばれ、試験官!」。世の中は様々な役割に支えられて成立しています。異なる立場に思いを馳せることができたとき、人はきっと優しくなれる。そんな考えにふと至ります。あ、まだ試験時間中でした――。
ここまで私の拙い編集後記を読んでいただいたあなたに、心より感謝します。引き続き、認定心理士の会の活動をよろしくお願いいたします。
(運営委員会委員:向居 暁)
-
認定心理士の会運営委員会〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13田村ビル内公益社団法人日本心理学会事務局jpa-ninteinokai@psych.or.jp
PDFをダウンロード
1




