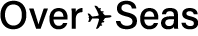- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 103号 病いと健康――ウェルビーイング再考
- 認知症とともに生きる人とのイギリスでの出会い
認知症とともに生きる人とのイギリスでの出会い
野村 信威(のむら のぶたけ)
Profile─野村 信威
2005年,同志社大学大学院文学研究科心理学専攻博士課程後期課程単位取得退学。博士(心理学)。専門は老年臨床心理学,質的研究法。2022年より現職。単著論文に「高齢者における回想法のエビデンスとその限界」『心理学評論』64, 136-154, 2020など。

筆者は2023年4月より在外研究でイギリスを訪れ,ヨーク・マインズ・アンド・ヴォイシズのファシリテータを務めるダミアン・マーフィ氏による認知症の診断後支援プログラム “A good life with dementia course” など先進的な認知症ケアの実践に触れる機会に恵まれました。なかでも認知症当事者として有名なジェームズ・マキロップ氏とウェンディ・ミッチェル氏のふたりと出会えたことは大きな収穫でした。
ジェームズ・マキロップ氏は1999年に59歳で多発梗塞性認知症と診断されたのち,認知症当事者のための組織であるスコットランド認知症ワーキンググループ(SDWG)を設立して初代会長を務めました。SDWGは日本を含む世界各国で同様の組織が設立される契機となっただけでなく,スコットランドの国家認知症戦略に多大な影響を与えました。筆者はマキロップ氏の自宅近くのカフェや公園を散策しながら話をうかがいましたが,診断から20年以上経過したことが信じ難いほど従来の認知症のイメージにあてはまらない力強さをその物腰から感じました。
ウェンディ・ミッチェル氏は2014年に58歳で血管性およびアルツハイマー型認知症の診断を受けましたが,それ以降も現在まで一人暮らしを続けながらブログや著作を通して情報を発信しています。これまで3冊の著作を刊行し,1冊目は日本語にも翻訳されています[1]。筆者は彼女にもインタビューを行い貴重な話をうかがいましたが,ここでは彼女の著作の一節[2]を紹介します。
最初のころ数日間タイピングをしなかった時期があった。この休息は私の手にとって歓迎すべきものだと思ったが,ふたたびキーボードを打とうとするとどうしていいか分からなかった(中略)私はいつも頭の中の霧を切り裂いていたこの能力を失ってしまうことに恐怖を感じ,その日以来タイピングをしない日は一日もない。(筆者訳)
こうした記述は,認知症とともに生きる人の支援に関心がある援助職者に重要な示唆を与えています。多くの認知症当事者にとって維持することの難しい能力,例えば文章を書く能力を彼女が保ち続けているのは,幸運にも症状の進行が遅かったからではなく,彼女自身が強い意志によってその能力を維持しようと努力し続けてきたためだと考えるべきです。実際に彼女は診断以降に(例えば紅茶を楽しむための味覚など)多くの能力を失ったことを明かしています。
それにもかかわらず,彼らはしばしば「本当の」認知症患者ではないと中傷されたり,例外的な認知症当事者だと見なされています。しかし筆者は,一般の人々が考える認知症患者と彼らの間には連続性があり,少なくとも症状の徴候が最初に現れた時点では違いがなかった可能性が捨てきれないと考えています。
診断後も以前の能力をある程度維持しながら活動する当事者の多くは65歳以前に発症し若年性認知症と診断されていますが,発症から1~2年という早い段階で診断を受けたことや(ただしマキロップ氏は正しく診断されるまで4年が経過しています),自ら症状に対処して認知症とともに生きる努力を続けてきたことも見過ごせない特徴です。
これまで認知症は,発症後は悪化の一途をたどり10年以内に重度に進行するとされてきましたが,こうしたモデルでは認知症とともにできる限りよく生きようとする人々について考慮されていません。筆者は一部の認知症の人がたどる「もうひとつの経路」を含む新しい認知症のモデルが必要だと考えていますが,筆者にとってこの渡英は研究の枠組みを超えた貴重な出会いの機会だと受け止めています。
- 1.ミッチェル, W. /宇丹貴代実訳 (2020) 今日のわたしは,だれ?. 筑摩書房
- 2.Mitchell, W. (2022) What I wish people knew about dementia (p.87). Bloomsbury Publishing.
PDFをダウンロード
1