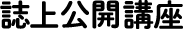- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 110号 ロスとグリーフ――うしなうことの心理学
- 集団の問題としていじめを理解する
集団の問題としていじめを理解する

水野 君平(みずの くんぺい)
Profile─水野 君平
2019年,北海道大学大学院教育学院博士後期課程修了。博士(教育学)。2023年より現職。専門は教育心理学。著書に『あなたの経験とつながる教育心理学』(分担執筆,ミネルヴァ書房),『はじめての発達心理学:発達理解への第一歩』(分担執筆,ナカニシヤ出版)など。
文部科学省の調査によればいじめの認知件数は年々増加傾向にあります。この認知件数の計上については議論の余地はありますが,いじめは決して許されるものではないのにもかかわらず,なぜ減らないのでしょうか。暴力的な人や共感性が低い人のせいでしょうか? もちろん,その可能性も考えられるかもしれませんが,ここでは「傍観者」について考えていきたいと思います。
いじめの四層構造
「いじめの四層構造」という言葉はご存じでしょうか。社会学者の森田洋司が提唱した理論で,いじめはいじめを受ける被害者といじめを行う加害者だけでなく,いじめを煽る「観衆」といじめを見て見ぬふりをする「(消極的な)傍観者」で構成されているという理論です(本稿では被害者や加害者以外の役割をまとめて傍観者と呼びます)。なぜ被害者と加害者だけでなく,傍観者が重要なのでしょう。いじめを煽ることで加害の継続や拡大を助長したり,見て見ぬふりをするだけでもいじめを容認することにつながるからだとされています。いじめを被害者と加害者だけの問題として考えるのではなく,周囲の人間を含めた教室の問題として考えようとしたのがいじめの四層構造の意義でしょう。いじめの四層構造は日本では有名な理論ですが,傍観者がいじめに重要な役割を果たしていることは日本だけでなく,海外でも知られています。トゥルク大学(フィンランド)のサルミヴァーリ(Salmivalli, C.)もいじめを集団プロセスとして捉えており,彼女が主導したフィンランドの国家的ないじめ防止教育であるKiVa(フィンランド語でいじめ反対を意味するKiusaamista Vastaanの略)でも消極的な傍観者とならないための教育的支援が含まれています。
傍観者の存在がもたらすもの
なぜ傍観者が重要なのでしょうか。それは,いじめが加害者にとっての利益となることに関係していて,サルミヴァーリらによるレビュー論文でその点が整理されています[1,2]。思春期では人気や注目を集めるなど自身の地位に関心が集まる時期です。いじめ加害者は周囲からの人気(社会的な地位)を求めていて,いじめ加害を行うことで周囲からの人気を得られるとされています。ここでいう人気とは社会的な注目度(カッコいいとか,目立っているなど)であり,周囲から受け入れられている程度ではありません。実際,地位を追求する子どもほどいじめ加害行為を行いやすく,いじめ加害者は人気が高い一方で周囲からそれほど好かれていません。「TV版のジャイアン」のようなガキ大将のイメージでしょうか。つまり,周囲がいじめ加害者をある意味で容認しており,この考えの重要な点はいじめ加害は不適応などの問題を抱えている子どもが無秩序に行うというよりも(もちろんその場合もありますが),地位の獲得という目的を持った手段としていじめ加害を行うという加害者像の転換でした。話を戻すと,いじめ加害者は周囲から人気があると見なされやすいということです。そして,いじめ加害者は人気が高いことが多いため,周囲はそれを簡単には止めにくいとされています。しかし,近年の研究では仲裁者は人気や好感度が高い子どもがなりやすい可能性があるものの,実際にいじめを仲裁してもその後の被害にはつながらないとわかりました3。このことを踏まえると,人権擁護の観点から「いじめは人権侵害で許されない」と訴えることも重要ですが,いじめのインセンティブに着目し「いじめはダサい」や「いじめはカッコ悪い」と訴えることも大事かもしれません。また,外国での知見を学校環境が異なる日本にどこまで適用可能か留意は必要ですが,いじめを仲裁して被る不利益は思うより少ない(ゼロかもしれない)と考え行動することも重要でしょう。
健全な状況のパラドクス
KiVaの話題に戻りたいと思いますが,KiVaは学校でのいじめを減少させるといった大きな成果を挙げました。単なる教育実践としてだけでなく大規模なランダム化比較試験の枠組みを用いて,その実践成果も実証的に裏付けられました。しかしその一方で新たな問題も浮かび上がりました。いじめが減っている学級でいじめ被害者であり続けることはそうでない学級の被害者よりも抑うつなどの指標が悪化したと報告されました[4]。いじめが減少し,学級の安全性が高まっていると考えられるのにもかかわらず,その中で被害を受けるとより悪影響を受けてしまうというものでした。この現象は「健全な状況のパラドクス(healthy context paradox)」として注目されるようになりました。その後,健全な状況のパラドクスはさまざまな国の研究でも報告され,頑健な現象だと明らかになりました。なぜ,健全な状況のパラドクスが起こってしまうのでしょう。ガランドー(Garandeau, C. F.)とサルミヴァーリのレビュー論文ではいくつか仮説が考えられています[5]。いじめの少ない環境で少数者である被害者は,①いじめ被害の原因をいじめが多い学校環境などに帰属できず自己非難的になりやく,②被害に遭っていない多数者と上方比較しやすく,③被害者同士で結束する機会が少なくなり,④周囲から被害者が非難されやすくなること,⑤友人の中でいじめられているのは自分だけと考えて苦しみ,⑥少数者であるがゆえに集団規範からの逸脱を経験しやすいということです。ただし,少数の被害者は集中的ないじめによってより深刻な被害に遭っている可能性や,他の被害リスクを抱えている可能性も考えられると考察しています。いじめが減ることは喜ばしいことですが,かえって少数の被害者を苦しめるのはいじめが集団プロセスであるからだといえるでしょう。この知見の教訓はいじめが減っている時に楽観視せず注意深く見守る必要があることだろうと思います。また,文部科学省の調査結果は認知件数に注意が向きがちですが,重大事態発生件数やその傾向と認知件数とのギャップにも注目すべきかもしれません。
このように,いじめは被害者と加害者だけではなく友人,学級など個人を取り巻く集団が深く関わる現象といえるでしょう。被害者や加害者だけに注目するのではなく,集団の視点からいじめの予防・対策を考えることが大事です。「いじめは教室の病」という喩えはなかなかに鋭い指摘だといえます。
文献
- 1.Salmivalli, C. (2010) Aggress Violent Behav, 15, 112–120.
- 2.Salmivalli, C. et al. (2021) J Res Adolesc, 31, 1023–1046.
- 3.Malamut, S. T. et al. (2022) Child Dev, 94,380–394.
- 4.Garandeau, C. F. et al. (2018) Int J Behav Dev, 42, 64–72.
- 5. Garandeau, C. F., & Salmivalli, C. (2019) Child Dev Perspect, 13, 147–152.
- *本稿は日本心理学会「高校生のための心理学講座2024」での講義内容の一部を加筆修正したものです。
PDFをダウンロード
1