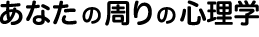- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 110号 ロスとグリーフ――うしなうことの心理学
- やる気がでないのは なぜだろう?
やる気がでないのは なぜだろう?
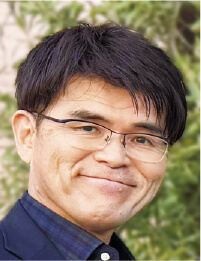
中谷 素之(なかや もとゆき)
Profile─中谷 素之
専門は教育心理学・動機づけ研究。博士(心理学)。2015年より現職。著書に『エピソードに学ぶ教育心理学』(共著,有斐閣),『ピア・ラーニング:学びあいの心理学』(共編著,金子書房)など。
「やらなきゃいけないのに,課題をやりたくない」「テストまで時間がないのに,ぜんぜんやる気になれない」。やる気がでないことに困ったり,悩んだりすることは,誰しもが日常的に経験するでしょう。やる気とはいったいどのようなものなのでしょうか。
動機づけとは
心理学ではやる気の問題を,動機づけ(motivation)という概念で考えます。動機づけとは,人間の行動を一定の方向に生起させ,維持,調整する過程のこととされており,人の起こすさまざまな行動の背後には,動機づけという心理学的要因が働いていると考えます。
やる気になる,やる気になれない,といっても,その様相はさまざまです。めんどうくさくて宿題なんてできない,という場合もあれば,問題が難しすぎて解く気になれないという場合もあるでしょう。動機づけに関する心理学理論でも,やる気をとらえる理論基盤を①認知論(個人の見方,考え方に基づく理論),②感情論(興味や不安,喚起など,感情に関わる理論),③欲求論(コンピテンスや自己実現など,生得的な欲求のレパートリーに基づく理論),④環境論(家庭や教室など主要な環境の影響を考慮した理論)の4つからとらえています[1]。 やる気といってもけっして単純ではなく,個人によって,また場面や状況によって,その生じるプロセスやメカニズムは同一ではありません。
また,動機づけと脳の関係を考えてみると,感情をつかさどる部位・回路,意図や創造性をつかさどる部位・回路など,それぞれが複雑な機能をもち,さらには動機づけの生起メカニズムではそれらがさらに複雑に組み合わさって生じるという,一層複雑な過程だと考えられます。
次からは,主に教育心理学研究の知見に基づいて,やる気がでないという状態の理解と,その改善について考えてみましょう。
やる気になれないとき―失敗とマインドセット
誰でも苦手なものや難しすぎる課題は,進んでやりたくはありません。昨今では中学受験など,早期の受験圧力も高まっており,学習内容も膨大になる傾向もみられ,勉強へのやる気をなくしがちで,無気力的になる子どもも少なくないでしょう。
心理学では,無気力になる子どもの認知について,「原因帰属」や「マインドセット(能力観)」などから説明しています。ここでは「失敗」や「努力」をどうとらえるか,がカギになります。
原因帰属では,「できなかったのは頭が悪いからだ」と考える失敗を能力に帰属する子どもは,「できなかったのは努力が足りなかったからだ」と失敗を努力不足に帰属する子どもに比べて,粘り強く取り組むことができず,パフォーマンスも芳しくない傾向があります。
またマインドセットでは,「人の能力は生まれつきで変わらないものだ」と信じる固定マインドセット(fixed mindset)の子どもは,勉強でも「数学が苦手なのはずっと変わらない」「自分にはセンスがない」と考えて,結果を得るための努力を避け,失敗に甘んじてしまいます。一方「人の能力は経験や努力によって変化・成長しうるものだ」と信じる成長マインドセット(growth mindset)をもつ子どもは,「努力しないと成功はない」「失敗しても,それは成長のための大事な機会だ」と考えて,努力を大事にし,意欲的に取り組む傾向にあります[2]。また,近年の研究では,学習心理学領域の認知負荷理論に基づいて,成長マインドセットを促した中学生では,学習の負荷の認知が低く,実際の学校での学習課題での保持と転移の成績が高いという結果も示され,学習への影響のプロセスの一端が示されています3。つまり「努力によって習得は向上する」と信じることで,実際の中学での学習課題での認知的な処理の仕方が変化し,高い負荷を認知しにくくなり,知識の保持や転移が向上したと考えられます。
動機づけを支える人間関係
さらに,認知や信念の個人内要因だけでなく,その人をとりまく人間関係という社会的要因も,動機づけの促進に重要な役割を果たします。
教室では,子どもは教師との関係性のなかで授業を受け,学んでいます。教師はその授業やクラスを指導・教授するため,教室の社会的関係や風土の形成に深く関連しています。学級の風土や環境を検討している教室の目標構造研究では,あるクラスや教科授業の社会的風土を,共有する規範や期待の点からとらえています。これまで,主に教室の学業面での目標構造研究が多くなされ,「このクラスでは努力や成長が重視されている」と認知する子どもは,動機づけなどの成果が高いことが知られてきました。しかし近年では,教室の社会的側面の目標構造研究もみられるようになり,「このクラスでは,相手の気持ちを考えることが大事にされている」などと認知する子どもにおいて,内発的動機づけや自己効力感が高まることが示唆されています[4]。さらに最近では,教室の学業的目標構造と社会的風土を組み合わせ,包括的な学習風土プロフィールを検討した例もみられ,そこでも,教室の学習面だけでなく,社会的なサポートや相互尊重の風土があることが,学業達成および学校適応において最も望ましいという結果が示されています[5]。
「やる気がでない」にどう向き合うか
以上は主に学校教育や教育心理学の領域からの知見であり,しかもぼう大な動機づけ研究のほんの一部しか扱っていません。ご関心のある方は動機づけ研究の専門書をお読みいただくとして,ここではごく簡単に「やる気がでない」子どもに,どのように向き合うかについて考えたいと思います。
前提として,人は誰しもやる気になれないときがあります。いつでもやる気に満ちた人はおらず,その状態がけっしておかしなことではない,という共感的理解が必要でしょう。そのうえで,原因帰属やマインドセットの考え方からは,失敗してもそれは自分の能力のなさを示すのではなく,学ぶ機会を得たのだと考えることを促す,挑戦する姿勢を評価し,われわれの能力や脳の可塑性,可変性に注目させることが大事でしょう。
また,教室の目標構造の観点からは,子どもが学ぶ教室の人間関係や環境に目を向け,教師や友人との関係のよい面に気づくよう促し,テストや成績の競争相手だけでなく,学びの資源を共有する仲間との学び(ピア・ラーニング)が重要です。教師は,子どもの失敗を恐れるのでなく,試行錯誤しチャレンジできる授業や人間関係に配慮することが求められます。
これらの子どもの動機づけの課題は,大人にも当てはまるものでしょう。面倒な時ややる気のでない時,仕事や活動への見方を振り返り,周囲の人間関係や環境の資源を再認識することは,行動を起こすためのきっかけになるのではないでしょうか。
文献
- 1.鹿毛雅治(2013)学習意欲の理論:動機づけの教育心理学.金子書房
- 2.Yeager, D., & Dweck, C. (2020) Am Psychol, 75, 1269–1284.
- 3.Xu, M. et al.(2021) J Educ Psychol, 113, 1177–1191.
- 4.大谷和大・岡田涼・中谷素之・伊藤崇達(2016)教育心理学研究, 64, 477–491.
- 5.Elizabeth, O. et al. (2024) J Educ Psychol, 116, 256–277.
PDFをダウンロード
1