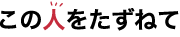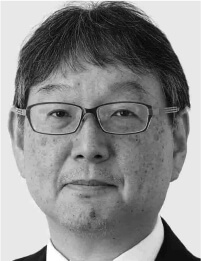
権藤 恭之(ごんどう やすゆき)
Profile─権藤 恭之
1994年,関西学院大学大学院文学研究科博士課程後期課程心理学専攻退学。博士(心理学)。東京都老人総合研究所研究助手,大阪大学大学院人間科学研究科准教授などを経て,2018年より現職。専門は高齢者心理学,老年学。著書に『100歳は世界をどう見ているのか』(単著,ポプラ社),『よくわかる高齢者心理学』(分担編集,ミネルヴァ書房),『Annual Review of Gerontology and Geriatrics, Volume 33』(分担執筆,Springer)など。
権藤 恭之氏へのインタビュー
─現在,先生が研究されているテーマについて教えてください。
加齢のポジティブな側面を明らかにすることです。そのために,70歳代から100歳代の高齢者を対象として,各年代の頭文字をとった「SONIC調査」を行っています。併せて,人々は年をとることをどう評価しているのかを検討するために,「加齢に対する信念の研究」を進めています。
─それぞれの研究の特徴と,研究から明らかになったことをご説明いただけますか。
SONIC調査は2010年から3年ごとに同じ人を追跡し,身体機能,認知機能や精神的健康などを測定する縦断研究です。いろいろな社会背景の人が含まれている多様性が特徴で,都市部と非都市部や,関東と関西の比較ができます。参加者の皆さんの職業もさまざまです。また,調査開始時点で90歳だった人の中で,100歳に到達された方とお亡くなりになられた方を比較すると,長生きな人の特徴を明らかにできます。この調査では,年齢が高くなると「老年的超越」と呼ばれる心の変化が起きていることが分かりました。老年的超越には,あるがままの状態を受け入れる「無為自然」や,善悪などの概念の対立の無効性や解消を認識する「二元論からの脱却」などの8つの因子があり,これらの側面が高まることで,身体機能の低下や自立が困難な状況であっても,精神的に健康で幸せでいることができると考えています。
国内外のこれまでの研究から,元気な老後をイメージしている人は,そうでない人よりも長生きするということも分かってきました。これらを受けて,加齢に対する信念の研究では,個々人が,加齢していくことのどこに一番引っかかりを感じているのかを把握して,その信念を少しでも変えられるよう社会的に介入することを目標としています。現在,信念は身体的変化や自己効力感など,5つの側面から測定できることが分かってきました。測定尺度が完成したところなので,さらにこういった点について研究を進めていきます。
─老年的超越の無為自然や二元論からの脱却が,私が現在研究している,物事をあるがままに受け入れ,現在の瞬間に価値判断をせず注意を向ける気づきであるマインドフルネスにも共通するものだと感じました。マインドフルネスを身につけるには,瞑想などの実践を繰り返すことが必要ですが,高齢者の方々は,年齢とともに,精神的健康を維持するために重要な要素を自然と身につけていったということなのでしょうか。
同時にいくつかの要素で変化していると考えています。経験によるものと,脳の生物学的加齢の2つが関わっており,年をとって機能が低下する中で発達するものだと考えています。
─高齢者を対象とした大規模縦断研究を実施するうえで,大変なことや工夫されていることは何でしょうか。
一人ではできない研究のため,多くの方に関わってもらう必要があり,組織が大きくなる点が大変です。関わるスタッフ全員が楽しめるように気を配っています。
工夫している点は,参加者の皆さんに,全体の進捗を共有したり,個別でご本人の結果を伝えたりしていることです。フィードバックを受けると「自分の結果が役立っているのだ」という実感を持っていただけるため,調査に継続して参加いただけると考えています。
─先生は学際的な研究や国際共同研究を多く行われていますが,その中でどのようなことを大切にされているのでしょうか。
医師や歯科医師との研究が多いのですが,その中で心理学ができる重要なことは「評価法を作ること」だと考えています。また,他の領域ではこう考えるのだ,とか,異なる分野ではこんな面白いことがあるのか,といったように,好奇心や開放性を持つことが大切だと思います。
国際研究をするうえでは,「躊躇しない」ことです。研究においては内容が面白いかが重要なので,考えたことをためらわずに伝えることが大切です。海外ではどのように研究を進めているのかをよく見ることも重要だと思います。
─今後の研究の方向性について教えてください。
年をとることが重荷にならないような研究をしていければ,と思っています。高齢者研究から見えてきたのは,幅広い年代の方々にどうアプローチしていくかが課題だということです。若い人だけでなく,高齢者も「高齢者は弱っているだろう」という思い込みであるエイジズムを持っているので,長生きはしたくない,100歳までは生きたくないと思っている人が多いのが現状です。しかし,ピンピンコロリとはいかなくても,もう一つの年の取り方があって,それでも不幸ではないということを知ってほしいのです。多くの人は,長生きするなら元気じゃなきゃ,と思っていますが,その思い込みを変えていき,「元気じゃなくても幸せなのだ」と思ってもらえるような研究をしていきたいです。年をとることをポジティブに思えるようになれば,エイジズムが減っていくはずです。高齢者になれば病気になるのは普通なのだと,根本的に考え方を変えていけたらと思います。死ぬ前に満足感が低下しないような死に方の解明を目指していきたいです。「こんなに生きると思っていなかったのに生きちゃった,でも思っていたより悪くないな」という感覚を得られるのだと,今後の研究でも示していきたいと考えています。
─研究の中で実現したいことをおうかがいさせていただきたいです。
海外で作成された尺度を訳すのではなく,日本で作成された尺度を海外で使用してもらえるようになることが夢です。日本語のニュアンスには難しいところがあります。例えば,年をとって弱っていくフレイルに対する不安尺度の作成の際には,「よぼよぼ」をどう訳すのかが議論になりました。また,老年的超越の概念には東洋的な部分があり,伝わりにくい側面もあります。西洋の文化をよく知ることが大事になってきますし,今後の日本のことをよく考えながら進めていきたいです。
また,余暇活動の研究を行う中で畑仕事が高齢者にとってさまざまなポジティブな影響を持つことなどが明らかになったのですが,このような科学的根拠を社会に発信し,それを推進していくことで,「やっていてよかったな」「これからやろう」という人が増えていくといいなと思っています。
─最後に,若手研究者に向けたメッセージをお願いします。
「心理学は最強の学問である」と思います。基礎を学んで方法論を身につければ,どんな業界やビジネスでも活躍することができます。心理学を学んでいることに自信を持って,科学的な視点を忘れずに,世界を変えるつもりで頑張ってほしいです。
聞き手はこの人
インタビューを終えて
高齢者の方々を対象とした大規模な縦断研究の第一人者でいらっしゃる権藤先生に,研究内容だけではなく,研究を進めるうえでの心得や研究者としてのあり方に関してまでお話をうかがう貴重な機会となりました。ご研究に関わるすべての方を大切にしながら,心理学の立場からできることを探り,その解明に向けて躊躇することなく研究を進めていく先生のご姿勢に,私も少しでも近づけるよう,尽力していきたいと思います。
私自身は,日常生活においてストレスと上手に付き合っていくための方法について研究しています。これまでには,ストレス状況への感情制御方略を自分で選択することの効果などについて検討してきました。最近は,マインドフルネスの一技法である「3ステップ呼吸空間法」に関心を持っています。気づく・注意を集中する・注意を広げる,の3段階からなる3ステップ呼吸空間法を実践することの効果を,実験を通して検討しています。精神的健康を維持しながら,高齢期に至るまで幸せに過ごすことができる社会の実現に向けた,知見の蓄積の一助となれるよう,研究に一層邁進していこうと,今回のインタビューを通して決意を新たにしました。
Profile─いまじょう のぞみ
早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程在学中。修士(医科学)。専門は感情心理学。筆頭論文にSelf-choice emotion regulation enhances stress reduction: Neural basis of self-choice emotion regulation. Brain Sciences, 14, 1077, 2024(共著)など。

PDFをダウンロード
1