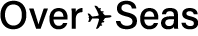- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 110号 ロスとグリーフ――うしなうことの心理学
- 妊婦と1歳の北極圏暮らし
妊婦と1歳の北極圏暮らし

山田 千晴(やまだ ちはる)
Profile─山田 千晴
博士(文学)。専門は認知神経心理学。早稲田大学人間科学学術院客員研究員,日本学術振興会二国間交流事業特定国派遣研究者を経て2024年より現職。現在二児の母。筆頭論文にEffects of the amount of practice and time interval between practice sessions on the retention of internal models. PLoS ONE, 14(4), e0215331, 2019など。
私は日本学術振興会(JSPS)の二国間交流事業特定国派遣研究者として,ノルウェーの北極圏に位置するトロムソに半年間滞在しました。「北極圏」と聞いて多くの方が想起するであろうイメージの通り,私はリビングで寝転びながらオーロラが夜空に揺れるのを眺めたり,極夜の昇らない太陽が山際を桃色に染める氷点下のなか,通勤をしていました(市街地なので,野生のシロクマに遭遇することはありませんでした)。
トロムソ大学(UiT)で高齢者の運動制御と認知機能の関連について研究をおこなうロドリゲス=アランダ先生とは2017年より交流があり,2018年に2か月ほどUiTに滞在したこともありました。折よく特定国派遣研究者の公募が始まり,これは行くしかない!と申請したのが2019年。日本とノルウェーにおける二段階審査を経て無事採用されたものの,コロナ禍に巻き込まれノルウェーでの滞在許可がいつ下りるのか不透明なまま待つこと数年。結局,日本人の入国制限が解除されたのは2022年2月で,申請時には単身で渡航するつもりだった私も一児の母となっていました。夫は常勤の職に就いていたため,比較的柔軟な働き方ができる私が長女を帯同することに。長女が1歳半になった2023年8月にトロムソへ旅立ちました。状況を鑑み渡航開始時期を調整してくださったJSPSとRCN(ノルウェー研究会議)には心から感謝しています。
海外での研究生活において経済力はもちろん重要ですが,健康こそ最大の資本ということも忘れてはなりません。というのも,私の場合は渡航直後に第二子の妊娠が発覚。長女妊娠時につわりが全くないタイプの健康優良妊婦だった私は「まぁ大丈夫でしょ」と滞在を継続しました。トロムソでの生活は快適で,現地の助産師から太鼓判を押されるほど母子ともに健康だったので結果的には問題なかったのですが,いま思えば大胆な決断です。余談ですが,つわりはその種類も重篤度も個人差が大きく,日常生活にどれだけ支障が出るかは本人すら妊娠するまで分からないということを,特に若い方はご自身の人生設計にかかわらず知っておいてください。とにかく「体調とお財布が許す限り海外には(遊びも含め)行けるときに行け」というのが1つめのメッセージです。ちなみに,特定国派遣研究者は派遣先の国の給与水準に沿って現地の研究推進機関から生活費が支給されるため,経済的に大変助かりました。
フィヨルドの中にあるトロムソは,UiTを抱える大学都市であるとともにオーロラの観光地としても有名で,諸外国から人が訪れます。治安もよく,どこでも英語が通じるので気楽に暮らすことができました。品揃えのよい輸入食料品店や現地の日本人コミュニティの存在も,子連れ妊婦にとって強力な支えでした。平日は8時~16時で娘を大学提携の保育園に預け,大学で実験や作業(北欧の保育支援は本当に手厚かった!)。ノルウェーの仕事上がりは早く,UiTは16時を前にあらゆる扉が施錠され職員証がないと通れなくなり,夕方には構内からほぼ人が消えます。保育園も16時半には閉園。当然,週末の大学は無人。郷に入っては郷に従えということで,私も土日は家で身体を休めたり長女と街へ出かけたりと(日本人の感覚では)休んでばかりの日々を送りました。日本からノルウェーの保育園に転園した長女は,野生のブルーベリーや雪遊びなどで北欧の大自然を存分に楽しみ,ノルウェー語も十分に理解していたようです。長女の適応力の高さには何度も感動し,何度も助けられました。日々重くなるお腹を支えつつ,活発な長女と毎日を精一杯楽しんでいたおかげで,日照不足の時期に抑うつ的になることも皆無でした。滞在中のトラブルも「これも人生の糧,いつか授業や学会で話のネタになる…」と思いながら乗り越えることができました。海外で研究する貴重な機会を得ることができた方は「“La oss kose oss(楽しもう)!”という気持ちを忘れずに」というのが2つめのメッセージです。
PDFをダウンロード
1