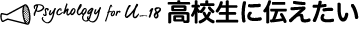- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 110号 ロスとグリーフ――うしなうことの心理学
- バイアスの心理学─意思決定・信念編
バイアスの心理学─意思決定・信念編

森 津太子(もり つたこ)
Profile─森 津太子
博士(人文科学)(お茶の水女子大学)。専門は社会心理学。著書に『社会心理学特論』(単著,放送大学教育振興会)など。共同監修に『ニュートン別冊 バイアスの心理学 増補改訂版』(ニュートンプレス)。
昼食に何を食べるか,動画サイトでどのコンテンツを視聴するか,インターネットで目にしたニュースや投稿をどの程度信じるかなど,私たちは,日々の生活の中で数多くの意思決定をし,同時に,何が正しく,何を信じるべきかといった信念も形成しています。そこには,気づかないうちに「認知バイアス」が関わっていることがあります。
錯思コレクション
私たちの研究チームは,こうした認知バイアスを紹介するウェブサイト「錯思コレクション100」を運営しています(URLは本稿末尾参照)。
「錯思」というのは造語で,ものの見え方に錯覚(錯視)があるように,考え方(思考)にも錯覚があるという発想から名づけました。『心理学ワールド』106号では,「錯思コレクション」を一緒に企画・制作した池田まさみ先生が「バイアスの心理学─知覚・認知編」と題して,記憶にまつわる認知バイアスなどを取り上げました[1]。今回は,意思決定や信念に関わる認知バイアスに焦点を当てて,その特徴と影響を考えていきます。
確証バイアスと現代社会
まずは,「確証バイアス」と呼ばれる認知バイアスから見ていきましょう。これは,自分の信念や期待に合う情報を重視し,それに反する情報を無視したり,軽視したりする傾向のことです。このバイアスが働くと,私たちは自分の信念を強化する情報ばかりに目を向け,反対の立場や新たな視点に触れる機会を減らしてしまいます。結果として,考えが極端になったり,適切でない信念を修正できなくなったりすることがあります。
いまの時代,私たちが日常生活の中で受け取る情報の量はかつてないほどに増加しています。このような情報過多の現代社会では,確証バイアスはとりわけ現れやすいと考えられています。情報を慎重に比較・検討することが難しくなったことで,気づかないうちに情報の取捨選択に偏りが生じやすくなっているのです。
また情報技術の進展により,自分の興味・関心に合う情報ばかりに囲まれやすくなりました。検索エンジンやSNSは,ユーザーの行動履歴や好みに基づいて情報を選別し,特定の傾向の情報だけを表示させます。こうしたしくみによって確証バイアスが助長されやすい情報環境がつくられているのです。
このような情報環境では,「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」といった現象が起こりやすくなっています。フィルターバブルとは,情報があらかじめ“フィルター”にかけられることで,異なる意見や価値観に触れる機会が減り,自分だけの“泡(バブル)”の中に閉じ込められたような状態を指します。一方,エコーチェンバーは,「エコー(こだま)」と「チェンバー(部屋)」を組み合わせた言葉で,閉ざされた空間の中で同じような意見が繰り返し反響し,それによって考えが徐々に強化されていく現象を指します。たとえば,SNSでは,自分と似た考えの人の投稿が優先的に表示されるため,異なる視点に触れる機会が少なくなり,自身の考えが一層強固になる可能性があります。
意思決定・信念に関わるバイアス
確証バイアスのほかにも,特に注意したい意思決定・信念にまつわるバイアスを3つ紹介しましょう。
①アンカリング
「アンカー(錨(いかり))」のように,最初に得た数値や情報が,その後の意思決定に影響を与えることがあります。ある実験では,実験参加者に「アフリカ諸国が国連に加盟している割合」を推定させる際,事前に任意の数値を提示しました。そして,その数値が正解の値よりも高いか低いかを判断させたうえで推定させると,高い数値が提示されたグループは推定値も高くなる傾向が見られました。たとえば,「10」または「65」を提示された際の推定値は,それぞれ中央値で25%と45%でした[2]。このように,最初に見聞きした情報は,たとえ無関係なものであっても基準(アンカー)となり,その後の判断に影響を及ぼします。たとえば,セールの前に表示される元値が,商品の価値判断に影響し,実際の価格がそれより安ければお得と感じやすくなるのも,アンカリング効果の一例です。
②フレーミング効果
同じ内容でも,どのような枠組み(フレーム)で伝えられるかによって,印象が変わり,意思決定を左右することがあります。「アジア病問題」として知られる実験では,あるアジアの国で感染症が流行し,600人が死亡する恐れがあるという設定のもと,実験参加者に2つの対応策のいずれかを選ばせました。すると,対応策が「200人が助かる」といったように肯定的に表現された場合,多くの人がリスクを避ける選択肢を選びました。しかし同じ内容が「400人が死亡する」と否定的に表現されると,よりリスクをとる選択肢を選ぶ傾向が見られました[3]。たとえば,同じ商品のレビューでも「10人中9人が満足」と言われると良い印象をもちやすくなりますが,「10人中1人は満足していない」と言われると,不安や疑念が生じやすくなります。
③真実性の錯覚
何度も目にする情報は,それが本当に正しいかどうかに関係なく,真実であるかのように見えてきます。ある研究では,実験参加者に以前に提示した誤情報を再提示したところ,その情報を「信頼できる」と判断する傾向が高まることが示されました。しかもこの傾向は,参加者がよく知っている分野に関する情報においても見られました[4]。このように,たとえその情報が事実でないと事前に知っていたとしても,「見覚えがある」という感覚が信頼感を生み出すのです。したがって,SNSなどで同じような表現や意見に繰り返し接していると,誤った情報であっても信頼してしまうかもしれません。真実性の錯覚は,SNSでの誤情報や,フェイクニュース(偽情報)の拡散にも関与していると考えられています。
認知バイアスとどう付き合うか
情報があふれる現代社会では,次々と押し寄せる情報にただ反応するだけで手一杯になりがちです。こうした状況のなか,最近では,情報を効果的に活用し,より良い意思決定を支援する手段として生成AIの活用が広がっています。しかし,AIもまたバイアスと無関係ではないという点には注意が必要です。現在の生成AIは,大規模言語モデル(LLM)を基盤とし,人間が生み出した膨大な文章(テキスト)を学習して構築されています。そのため,学習に用いられたデータに偏りがあると,その偏りがAIの出力にも反映させることがあります。たとえば,ある職業については男性的,別の職業については女性的に描かれた記述が多ければ,AIもそれを踏襲した表現をする可能性があります。AIは中立的に見えるかもしれませんが,実際には私たち人間の価値観や思考のクセが反映されているのです。
認知バイアスは誰にでも自然に生じるもので,必ずしも悪いものばかりではありません。実際,「バイアスの心理学─知覚・認知編」1で紹介されたように,不安や落ち込みを和らげたり,心の安定や自己肯定感を支えたりするようなバイアスも存在します。私たちの研究グループでは,多様な認知バイアスを分類・整理し,その背景にある共通の心のしくみや働きを明らかにすることで,バイアスとうまく付き合うための手がかりを探っています。認知バイアスを完全になくすことは現実的ではありませんし,それが望ましいことなのかも定かではないからです。
研究の結論が出るにはまだ時間がかかりますが,それを待つ間にも,私たち一人ひとりが日常生活の中でできることはあります。まずは,自分にも認知バイアスがあることを自覚することが第一歩です。「自分に都合の良い情報だけを信じていないか」「表現の仕方に影響されていないか」「何度も見た情報だからといって正しいと感じていないか」など,時々立ち止まって自分に問いかけてみましょう。また,違和感を覚えたときには,別の視点や情報源を探したり,他の人とそのことについて話し合ってみたりすることも効果的です。結論を急がず,一度立ち止まって考える習慣をもつことで,より適切な判断ができるようになるはずです。こうした姿勢は,単なる情報リテラシーの向上にとどまらず,多様な価値観を尊重し,他者とより良い関係を築くためにも役立ちます。
認知バイアスは避けることのできない心の働きですが,それを理解し,向き合うことで,情報に満ちた社会をより賢く,柔軟に,そして主体的に生き抜く力を育むことができると信じています。
ブックガイド
- 『錯思コレクション100』https://www.jumonji-u.ac.jp/sscs/ikeda/cognitive_bias/
- 「思考の錯覚」である認知バイアス100種類を日常生活の例や1分動画でわかりやすく学べるサイト。
文献
- 1.池田まさみ(2024)心理学ワールド, 106, 42–43.https://psych.or.jp/publication/world106/pw21/
- 2.Tversky, A., & Kahneman, D. (1974) Science, 185, 1124–1131.
- 3.Tversky, A., & Kahneman, D. (1981) Science, 211, 453–458.
- 4.Fazio, L. K. et al. (2015) J Exp Psychol. Gen, 144, 993–1002.
PDFをダウンロード
1