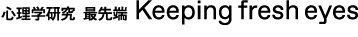- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 110号 ロスとグリーフ――うしなうことの心理学
- 社会の知られざる仕事と共に歩む犯罪心理学
社会の知られざる仕事と共に歩む犯罪心理学

入山 茂(いりやま しげる)
Profile─入山 茂
東洋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士(社会心理学)。専門は犯罪心理学,法と心理学,社会心理学。著書に『司法・犯罪心理学入門:捜査場面を踏まえた理論と実務』(共編著,福村出版)など。
はじめに
社会には,メディアで注目される機会は少ないが,重要な役割を果たす仕事が数多く存在する。これらの仕事は広く認知されていないため,問題が発生しても現場の人々が適切な支援を受けにくいことがある。筆者も犯罪心理学の研究を続けながら,航空会社のグランドスタッフとして長年勤務している。この経験を通じて,社会にあまり知られていない仕事の現場で生じる司法・犯罪関連の問題に関心をもち,心理学の視点から現場に寄り添った解決策を模索する研究を進めている。本稿では,いくつかの研究事例を紹介する。
検視に関する研究
検視は,法医学等の専門家の支援を受けながら,届け出された遺体の状況を調査し,他殺どうかを判断する業務である。検視の多くは,刑事訴訟法第229条第2項に基づき,検察官に代わって検視官(任期制で死体の取扱いを専門とする警察官),補助者(検視官を補助する警察官),所轄警察署の刑事課強行犯係(初動対応を担当する警察官)が連携して行う。
検視の現場には,誤った判断につながるリスクのある情報が潜んでいる。例えば,遺書が残されている場合(以下,遺書情報とする),人は対象の死亡事象について自殺である可能性を直観的に高く見積もることが経験的に指摘されている[1]。こうした経験則を実証的に検討することにより,検視官等を育成するための資料や検視時の注意点として活用できる。
そこで,大学生を対象に架空の死亡事例を提示し,自殺であるか他殺であるかの判断を求める実験を行った[2]。その際,遺書情報の提示の有無と自殺を支持しない情報の提示の有無を操作した。その結果,遺書情報が提示された条件では,遺書情報が提示されなかった条件と比較して,自殺の可能性をやや高く判断していたことが示された。この知見は,遺書情報に触れることにより,人は対象の死亡事象について自殺の可能性をやや高く見積もる傾向があることを示唆している。
損害サポートに関する研究
損害サポートは,損害保険会社の業務であり,事故の損害調査や相手方との交渉を通じて保険金の支払可否を判断し,適切な支払いを実施する業務である。近年,海外旅行保険の加入者による虚偽の携行品損害の申告(例:空港でバッグをひったくられたと偽る)による不正請求が問題となっている。不正請求の特徴を検討することにより,損害調査時の判断に活用することができる。
そこで,ある保険会社の一定期間の保険金請求事例を調査し,不正請求(保険金詐欺の可能性が高く,支払いに至らなかった事例)と一般請求(不正請求に該当しない事例)に分類し,その傾向を分析した[3]。その結果,一般請求ではスーツケース等の1点の破損が主な申告内容であったのに対し,不正請求では全ての申告内容がパソコンや高級ブランド品等の複数の高額な携行品の盗難被害であったことが示された。この知見は,時間を費やして被害状況等をより詳しく調査するべき事例かを見極めるための基準として活用できる可能性がある。
おわりに
本稿で紹介した研究には課題もある。検視現場における経験則を検討するならば,検視官等を対象に実験を行う必要もある。対象の保険会社や期間を拡げて調査を行った場合,携行品の破損を申告した不正請求事例が存在する可能性がある。これらの課題について,どのようにして現場から協力を得て検討を行うかを考える必要がある。しかし,現場の人々と人間関係を築き,課題解決を検討することは,心理学の視点から現場に寄り添った解決策を模索する研究の醍醐味でもある。
文献
- 1.城祐一郎(2022)警察官のための死体の取扱い実務ハンドブック:事例等解説や用語解説で学べる実務の要点.立花書房
- 2.入山茂(2020)応用心理学研究,46,149-157.
- 3.染矢瑞枝・阿部光弘・入山茂・桐生正幸(2017)日本応用心理学会第84回大会発表論文集,121.
PDFをダウンロード
1