- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 109号 アートは人と人の間で生まれる
- 私のワーク×ライフサイクル
私のワークライフバランス
私のワーク×ライフサイクル
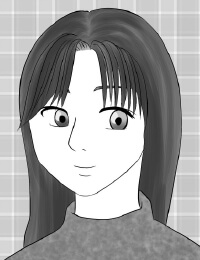
小田 友理恵(おだ ゆりえ)
Profile─小田 友理恵
2020年,法政大学大学院人間社会研究科人間福祉専攻博士後期課程修了。博士(学術)。2025年4月より現職。専門は臨床心理学。分担翻訳に『心理学者の考え方:心理学における批判的思考とは?』(新曜社)など。
普段より臨床,研究において「ライフ」に関わっていらっしゃる小田先生。臨床・研究と日々の生活との,身体を通した結びつきの大切さを語っていただきました。
私の研究テーマは,臨床心理学における科学者-実践者モデルです。資格取得のために入学した大学院で抱いた,臨床をするのになぜ研究をしなくてはいけないの? という素朴な疑問から探究が始まり,今に至ります。そしてありがたいことに現在,私の「ワーク」は臨床実践とその研究(および教育)です。
ライフにはご存じのとおり生活・生命・人生といった意味がありますが,私のワークはまさに「ライフ」に携わるものであると意識させられることが多くあります。臨床では,相談にいらっしゃる方々や一緒に働く方々と過ごす時間の中でそのことを実感しています。また,研究でもライフを扱っていることにあらためて気づかされる瞬間があります。臨床心理学史の研究では臨床心理学という学問の歴史を紡いできた先達の生き様を知り,質的研究ではインタビュー調査やテクストデータから研究協力者の人生の一端に触れ,量的研究では統計処理をとおして得られた結果からある集団の声なき声が聞こえるような気がしました。臨床もその研究も,人々のライフそのものに触れる性質を持ちます(よく考えると,ライフに関係しないワークはこの世には存在しないとも言えますが)。そのため,学問としての臨床心理学は,その主たる基盤を研究論文や学術書に求めますが,それらだけでは決して成り立たず,大学や大学院のカリキュラムには実習や演習の科目が組み込まれています。
日々の生活が生命を支え,人生を織りなしていくことを考えると,ライフの根幹は日々の生活にあるのだと,当たり前のことながら近頃気づきました。衣服を身につけ,食べものを準備して(あるいはしていただいて)食し,土地と家に住まう。家族や友人とともに時を過ごす。美味しいものを味わう。テレビやインターネット,本などで新たな世界や異なる価値観に出会う。趣味のコミュニティに参加する。エンターテインメントや芸術作品など誰かの創造性に感情を揺さぶられる。旅に出て知らない土地を訪れる。運動して自分の身体と向き合う。動植物や自然に接する。笑ったり泣いたり怒ったり。時には疲れたり,落ち込んだり,打ちひしがれたり。それでも,誰かの存在や優しさに救われて,また少しずつ立ち上がる。そして今度は自分自身が誰かの力になれるようにと願う。
研究会や学会への参加といったアンオフィシャルな自己研鑽の機会を含む仕事の時間と,それ以外の私的な時間,その中間もあわせたこれまでの人生すべての時間の体験が織り重なって,「今ここ」の私という身体と私の身体感覚が形づくられています。ちなみに,このような見方や考え方は臨床技法であるフォーカシングを考案したジェンドリンの哲学から学びました。そして,その身体でもって臨床や研究の場に立ち,同じように生きている身体を持つ目の前の人(あるいは誰かが過去に発信したもの)と交流をし,その瞬間に今までなかった何か新しいものが生まれるのを目の当たりにしたときの驚きと感動は,私の人生にとってかけがえのないものです。
さて,本稿のテーマは「私のワークライフバランス」でした。一般的に語られる際の意味とは少し異なるのかもしれませんが,今の私にとってのワークとライフは「ライフがワークを紡ぎ」「ワークがライフを豊かにする」という循環関係にあります。この関係は,私自身の研究テーマである科学者-実践者モデルにおける科学と実践の関係に似ているのかもしれません。これからも,いただいたお仕事と日々の生活を大切に,臨床と研究の両立の道を歩んでいきたい,と考えています。
PDFをダウンロード
1




