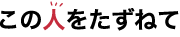木村 元洋(きむら もとひろ)
Profile─木村 元洋
2007年,北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。2007年に日本学術振興会特別研究員PD(名古屋大学・ライプチヒ大学),2010年に同・海外特別研究員(ライプチヒ大学),2011年に産業技術総合研究所ヒューマンライフテクノロジー研究部門研究員,2021年に同・ヒューマンモビリティ研究センター研究チーム長を経て,2023年より現職。専門は生理心理学。著書に『生理心理学と精神生理学 第II巻』(分担執筆,北大路書房)など。
木村 元洋氏へのインタビュー
─先生の研究テーマについて教えてください。
私は学部・修士・博士時代を北海道大学で過ごしましたが,その頃から取り組んできたのは,脳波・事象関連電位を使った生理心理学研究,特に人間の視覚についての研究です。これまでの研究でわかったことは,私たちの視覚システムは,対象物の動きの中にある規則性をもとに,対象物の一瞬先の状態を自動的に予測しているということです。例えば,キャッチボールの際,私たちは飛んできたボールを難なくキャッチできます。人混みの中でも,人とぶつからずにスイスイ歩くことができます。こういった行動の背景には,視覚システムの自動的予測の働きがあると考えられます。さらに,この自動的予測は,対象物が予測と異なる動きをした場合,それに瞬時に気づくことも可能にします。この予測の働きには個人差もあります。脳波・事象関連電位を活用することで,普段私たちが意識せずに行っている「見る」という行為を支えている仕組みの一端を知ることができます。
─博士のころに行っていた研究を今も継続しているのですね。
少し脱線しますが,私は学生時代,文学や芸術への関心が強くて,心理学にはあまり興味がなかったのですが,何の因果か,偶然出会った生理心理学がじわじわと面白いものになり,それが仕事になりました。手を動かして実験を重ね,物事の仕組みを紐解いていく地道なプロセスが気質に合っていたのかもしれません。心理学に興味が薄かったぶん,研究テーマを決めるのに苦労しましたが,修士の頃,それまで報告のなかった脳波・事象関連電位成分を運よく発見し,それが自分のコア・テーマになりました。学位取得後も,学振(日本学術振興会)の特別研究員PDや海外特別研究員として,日本とドイツを行き来しながらこのテーマに没頭しました。その後,産業技術総合研究所(以降,産総研)に就職しましたが,今でもこのテーマは継続しています。若い頃に比べてかけられる時間はだいぶ減りましたが,逆に国内外の若手との連携が拡がっていますので,今はそちらを中心に進めています。
─産総研に所属すると,実験室実験よりも,現実場面に近い応用的な研究に取り組む必要があると思いますが,研究への取り組み方に変化はありましたか。
産総研に入ってすぐに企業との共同研究をはじめましたが,最初はうまくやるのが難しかったですね。例えば,企業からリクエストの多いお題の一つは,実環境でサービスやプロダクトを利用している人間の心理的状態を脳波・事象関連電位で評価したい,というものです。一方,アカデミアの研究では,ノイズの少ない実験室で,統制された実験パラダイムを用いて脳波・事象関連電位成分を計測するのが主流です。最初の2~3年,このギャップに悩みました。それまでの自分が「現実世界の人間」を相手に研究できていなかったことを突き付けられた,とも言えますね。これを打開するために目指したのは,実環境の活動場面で汎用的に使えて,かつ企業の関心の高い心理的状態(例えば,集中,努力,楽しさなど)にアプローチできる生理心理学的評価技術を作ること。そして,それらの心理的状態がどんな仕組みで生まれるかを説明する包括的な理論を作ることでした。こういった仕事に一緒に取り組める同僚にも恵まれ,評価技術開発と理論構築をうまく進めることができました。少し具体的にお話すると,例えば,私たちは運転中,何気なく車速を上げ下げしていますが,これは自身の能力とタスクの負荷のバランス維持の観点から理解できます。車間距離や交通環境に応じてタスクの負荷は刻々と変化しますが,私たちはこの負荷の変化に合わせて車速を上げ下げし,自身の能力発揮レベルを一定範囲内に収めているわけです。しかし,約束に遅れそうなときなどは速度を上げざるを得ません。そんなときは,高い負荷に見合うよう能力発揮レベルを高めて,集中・努力して運転する。楽しさも変化する。このように,負荷と能力のインタラクションの産物として心理的状態を位置づけ,それを脳波・事象関連電位,瞬目信号,心臓血管系反応などの複数の生理反応で捉える。これが私たちの基本的な研究スタイルです。
─今後の研究の展開について教えてください。
ここ最近は心理的ウェルビーイングの研究にも着手しています。産業界でもホットなトピックの一つですが,研究としてどう扱うかは悩みますね。社会心理,発達心理,人間工学など,多様なバックグラウンドの人間研究者からなるプロジェクトチームを作り,まずはウェルビーイングをどう捉えたら面白い研究ができそうか,心理学はもとより,哲学や社会学をはじめとする色々な分野を勉強しています。また,先ほど述べた能力発揮とウェルビーイングの関係についての考察も進めています。さらに,生理心理計測についても,先ほど挙げた中枢・末梢系に加え,内分泌系や免疫系も含めた実験系の構築を進めています。ウェルビーイングをどう評価し,どう働きかけ,どう産業応用につなげるか,私たちなりの知見を発信していきたいですね。
─最後に,若手研究者に向けたメッセージをお願いします。
有益なメッセージになるかわかりませんが,大きく三つあります。一つ目は,「良いタスクを与えてくれる人との関係を大切にすること」です。良いタスクが目の前にないと力が湧いてこないのが人間の本性でしょう。学生時代から今までを振り返ってみると,その時々で,「難しそうだけどやるに値すると思えるタスク」を目の前に示してくれる人との幸運な出会いに恵まれたと感じます。そんな出会いを大事にしてほしい。二つ目は,「ときに自分の職能を広く捉えてみること」です。研究を続けていると,専門外のテーマに取り組まなければならない場面も少なからず出てきます。そんなとき,自分を大きく「人間研究者」として捉え,前向きに取り組んでみてほしい。自分自身の能力についての思わぬ発見や,研究者としてのスケールの広がりにつながると思います。三つ目は,「心理学以外の教養も大事にすること」です。面白い心理学研究をされている方には,心理学以外の教養にも富んだ方が多い。そういった教養は,心理学の活かし方を俯瞰的に捉えることにつながります。幅広い教養に裏打ちされた,鋭くユニークな「人間の見方」ができる研究者。そんな研究者に私も憧れますし,皆さまにもそんな研究者を目指してほしいですね。
聞き手はこの人
インタビューを終えて
木村先生は生理心理学の基礎研究で国際的に活躍されているトップランナーです。産総研では,企業との共同研究を数多く手がけられるなど,基礎のみならず応用まで高いレベルの研究を行われています。幅広く研究を行うことは,やりたいと思えば誰でもできると思いますが,それを高いレベルで行うことは容易ではないと考えています。微視的になりすぎるか,大雑把になりすぎてしまうためです。お話をうかがう中で気づいたことは,木村先生が,研究という営みを俯瞰して見つめることと,研究対象を細かくていねいに調査することを同時に行われているということです。私の能力や資源だけでこれができるかと問われると返事に困りますが,他の人たちも巻き込んで,よい仕事・研究をできるようになりたいと感じました。
私自身は,認知心理学のノウハウを製品やサービスの開発に生かすべく,まずは博士課程まで進み,アカデミックな研究を学びました。今年度からはIT企業で,ユーザーの製品利用体験の調査業務に従事することになりました。開発の現場で心理学をどう役立たせるのか,私にとっての「武器」とは何か,それをどうよい仕事につなげていけるのか,自分なりに考えていきたいと思っています。
Profile─いわね はるか サイボウズ株式会社開発本部。筑波大学人間総合科学学術院人間総合科学研究群博士後期課程修了。博士(心理学)。専門は認知心理学・認知科学。共著論文に「店内で商品を探す行動とサインの相互作用,そしてその加齢変化」『認知科学』31, 573–586, 2024など。

PDFをダウンロード
1