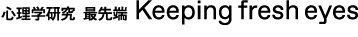- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 109号 アートは人と人の間で生まれる
- 「ヒューマンエラー」から安全を考える
「ヒューマンエラー」から安全を考える
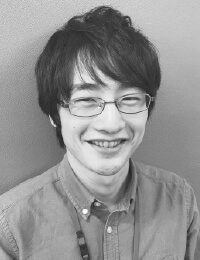
西村 春輝(にしむら はるき)
Profile─西村 春輝
筑波大学大学院人間総合科学研究科3年制博士課程修了,博士(心理学)。2021年より現職。専門は臨床心理学,産業組織心理学。筆頭論文にCurrent Psychology, 41(5), 2896–2907, 2022など。
私たちは日常生活やニュース,そして心理学の研究の中で「ヒューマンエラー」という言葉をよく耳にします。仕事上のちょっとしたミス,交通事故,医療事故,航空機のトラブルなど,さまざまな場面で「ヒューマンエラーが原因だった」と言われることがあります。たとえば,幼稚園や保育園の送迎バスに園児が取り残され,熱中症で亡くなってしまうという痛ましい事故が数年前に相次ぎました。この事故では,スタッフによる「思い込み」「確認不足」といった「ヒューマンエラー」が問題視されました。では,「確認不足」のような「ヒューマンエラー」を原因とみなすことは将来の事故の再発防止に役に立つのでしょうか。
シドニー・デッカーによると,「ヒューマンエラー」という表現はしばしば後知恵(hindsight)として用いられています[1]。普段,それなりの確認方法で問題なく運用されていれば,その確認は「ヒューマンエラー」とは呼ばれません。しかし,ひとたび事故が起きると,後から得られた情報と照らし合わせて,その時の行動が正しかったかどうかの評価が第三者によって行われます。照合の結果,あるべき姿と比較して不十分な点が見つかると「ヒューマンエラーが原因で事故が起きた」と論じられることになります。
私は,仕事上,企業や公的機関の事故報告書を読む機会がありますが,「不注意」「確認不足」「意識の欠如」といった「ヒューマンエラー」が原因として挙げられることは少なくありません。より専門的な表現として「不安全行動」や「危険感受性」などが代わりに用いられることもあります。このような原因論から導かれる典型的な再発防止策は,「確認の徹底」「ルールの遵守」のような精神論になりがちです。
推測ですが,園のスタッフは,ふつうに確認をしていたと思われます。たとえば,車内の隅々まで確認せずとも,運転席側から座席全体をざっと目視する,降りてきた園児の数を数えるといった方法でも通常は問題ないと思います。さらに,バスから園児は勝手に降りるでしょうから,降りるところを見ていれば,それで確認したとも言えるでしょう。これを「ずさんな管理体制」と後から指摘することは容易ですが,このような後知恵的な解釈では,事故がなぜ起こったのかを説明できません。事故の原因を理解するために最も重要なのは,当事者が何故そのような行動をとったのか,当事者の立場になって理解することです。
私の所属する研究所の大先輩である狩野広之氏は1959年の『不注意物語』という著書の中で「不注意は原因ではなく,むしろ結果」であり,「不注意の発生する条件」を研究するべきと指摘しています[2]。また,近年ではデッカーをはじめとするヒューマンファクターズの専門家は,「ヒューマンエラー」を原因ではなくシステムの一部とみなし,事故がなぜ起きたのかを問うことは,よりよい組織を作るための学習の機会ととらえることができると考えています[1]。
「ヒューマンエラー」を原因とみなし「ヒューマンエラー」を防ぐことばかりに注力してしまうと,より上流にある社会文化的背景,組織の仕組みや文化,管理の方法,仕事のやり方を問うことができなくなり,本来の目的である事故防止から視点が逸れてしまいます。一方で,より上流の問題も含めて事故をシステムとして理解していくことで,将来の事故を減らすことができるかもしれません。「ヒューマンエラー」をどのように理解し,付き合っていくかを考えるのが今の私の研究テーマのひとつです。
文献
- 1.デッカー,S./小松原明哲・十亀洋監訳 (2010) ヒューマンエラーを理解する:実務者のためのフィールドガイド.海文堂出版
- 2.狩野広之 (1959) 不注意物語:労働災害の事例研究集.労働科学研究所
PDFをダウンロード
1