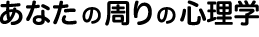- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 109号 アートは人と人の間で生まれる
- “スイーツ心理学”ってなんですか?
“スイーツ心理学”ってなんですか?

大本 浩司(だいもと ひろし)
Profile─大本 浩司
専門は人間工学・心理工学。博士(学術)。企業(電気メーカーや輸送機器メーカー)での研究開発を経て,2017年より現職。心理学の知見や手法の産業応用に取り組む。
スイーツ心理学は,甘い食べ物が人々の心理や行動に与える影響を研究する学問であり,ポジティブな感情を喚起する仕掛けを考案することで,社会的な問題解決を目指しています[1]。日常的にもスイーツを食べて気持ちを切り替えて仕事を頑張った経験や,疲れた時にスイーツを食べて癒された経験をした人も多いのではないでしょうか。また,友人や家族と一緒にスイーツを楽しむことで,社会的な絆を深めた経験もあるのではないでしょうか。帝塚山学院大学では,「おやつと心の,ふしぎな関係。」というキャッチフレーズを付けたロゴマーク(図1)を掲げて,このようなスイーツの喫食に伴う心理や行動について心理学的に研究して,学問としての知見を蓄積しています。また,社会的な文脈の中で心理学の知見や手法を駆使した問題解決に取り組んでいます。
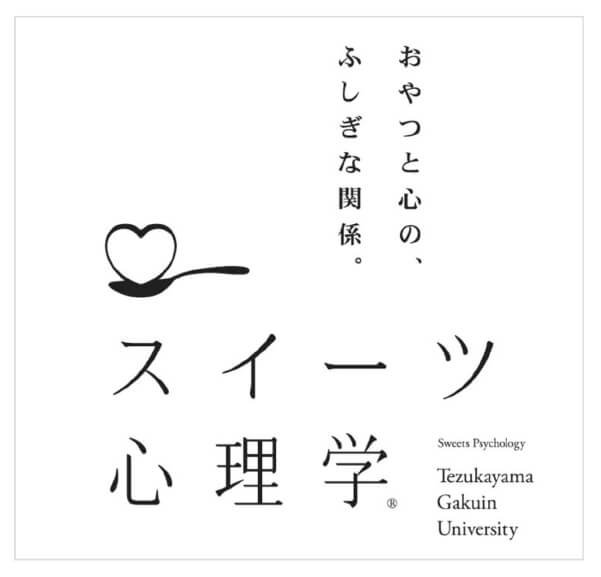
スイーツに特化した心理学
スイーツは,日常的に消費される食品であり,研究者にとっても実験協力者にとっても非常に身近なものなので,ポジティブ感情を喚起する実験刺激としても有望であると考えられます。スイーツの喫食は五感を伴った心理的なプロセスとして捉えることができるため,知覚・認知心理学の視点からスイーツがもたらす心理効果やそのメカニズムについて探求することができます。また,スイーツは社会・文化的にも特別な意味を持つことが多く,社会的なつながりやコミュニケーションの場面で機能的に作用していると考えられるため,社会心理学の視点からスイーツがもたらす効用やそのメカニズムについても探求することができます。このようにさまざまな心理学領域の視点からスイーツに特化した研究を行うことで,日常生活におけるポジティブ感情に関する学術的な知見を幅広く蓄積することができます。
スイーツの心理学的評価
スイーツを対象とした心理学研究に取り組む際の評価手法の一つとして心理尺度を用いた主観データの収集があります。心理学の尺度構成法に基づいてスイーツに特化した心理尺度を構築することで,スイーツの喫食に関わる抽象的な概念を定量的に評価することができます。具体的には,スイーツ心理尺度(短縮版)[2]がすでに作成されており,スイーツに関わる心理状態を網羅的に測ることができます。スイーツ心理尺度(短縮版)は,「目的」尺度(6因子),「購入前から食べる前」尺度(2因子),「食べている時から食後」尺度(6因子)の3尺度から構成されており,スイーツの購入前から摂取後までのプロセスの中でさまざまな心理的変化を捉えることができます。このスイーツ心理尺度(短縮版)は,スイーツに特化したさまざまな心理学研究に活用することができます。加えて,現実場面におけるスイーツの消費者心理を網羅的に把握する際にも利用できますので,企業におけるマーケティング研究や商品開発においても役立てられると考えられます。
スイーツの心理効果
スイーツがもたらす心理効果に関する筆者らの研究として,「チョコレート喫食による心理効果と有効視野の関係」があります[3]。この研究では,普段から好んで食べているチョコレートを喫食することでポジティブ感情が喚起されて,視覚的注意範囲である有効視野が拡大されることを示しています。つまり,チョコレートを食べて快感情が生じて,その結果として人間は一時的に通常より広範囲の視覚的な情報を取得して処理できると考えられます。例えば,スポーツ選手が好みのチョコレートを直前に食べてから競技すると,いつもより周りへの注意が広がって好成績を収めることができるかもしれません。このようにスイーツの喫食は,人間がアクティブに行動する場面でも効果的に作用することが示唆されています。
スイーツ心理学の産業応用
心理学の知見や手法を社会的な文脈の中で問題解決に活かす場合,人間中心設計に基づいた取り組みが有効であると考えられます[4]。人間中心設計は,モノ中心ではなく,人を中心としたモノやサービス作りのプロセスや方法論を体系的に整理したもので,実際に企業の研究開発において心理学に関する知見や手法が活用されている事例もあります[5]。例えば,スイーツを対象とする場合であれば,スイーツを食べる体験を特別なものにするために,フィールド調査から消費者のポジティブ感情に影響を及ぼす要因を抽出した上で解決案を策定します。また,消費者からのフィードバックをアンケート調査やインタビュー調査を通じて収集することで,スイーツの開発やマーケティング調査へ役立てられます。スイーツ心理学では,このような人間中心設計に基づいた検討を重ねることで,より効果的な問題解決へと導くことができると考えています。その際,ポジティブ心理学や感性工学の知見を踏まえることで,より人間理解に基づいた商品やサービスの開発へ展開できると考えられます。
スイーツ心理学による社会連携
スイーツ心理学では,学術研究にとどまらず,スイーツに関わる人間特性の理解に基づいた社会的な問題解決を目指しています。例えば,帝塚山学院大学では,スイーツ心理学の実習授業が行われています。この授業では,食品関連企業の協力を得て,人間中心設計に基づいて各種スイーツの体験価値を分析して,消費者視点から現状の問題を解決するアイデア考案を行っています。さらに,地域密着型の社会貢献として,地元企業と連携した商品開発を行い,地域活性化を目指したイベントで販売促進活動などの取り組みを行っています[1,6]。
スイーツ心理学の展望
スイーツ心理学は,日常的にご褒美として消費されることが多い「スイーツ」という身近な嗜好品を研究対象としています。このスイーツは,一般的に人々の記憶の中ではポジティブ感情と結びついていることが多く,心理的な報酬としての役割を持っています。われわれがスイーツを摂取すると脳内の報酬系が活性化して,特定の行動が条件づけされて習慣化することがあります。この点は注意しないと過食や中毒などの問題が生じてしまいます。スイーツ心理学では,このネガティブな側面に配慮しつつ,特にポジティブな側面に焦点を当てた心理学として取り組んでいます。日常生活の中でスイーツを楽しむことは,心の健康や幸福感を高める手段として重要であり,さまざまな心理学の知見や手法を駆使して幸せの輪を広げる貢献をしていきたいと思っています。
文献
- 1.大本浩司 (2022) エモーション・スタディーズ, 8, 23-27.
- 2.大本浩司他 (2023) 帝塚山学院大学研究紀要, 3, 55-74.
- 3.山中仁寛他 (2024) 人間工学, 60, 43-50.
- 4.黒須正明 (2013) 人間中心設計の基礎. 近代科学社
- 5.大本浩司他 (2011) 国際交通安全学会誌, 36, 14-23.
- 6.大本浩司他 (2021) 帝塚山学院大学研究紀要, 1, 83-96.
PDFをダウンロード
1