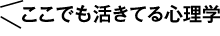- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 109号 アートは人と人の間で生まれる
- 教え導く者から,立ち会える者への変化
教え導く者から,立ち会える者への変化
前川 麻依子(まえかわ まいこ)
Profile─前川 麻依子
2003年より教職に就く。2015年,北海道教育大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻専門職学位課程修了。専門は特別支援教育。

Aちゃんが風邪でお休みしていた日のことです。同じクラスのB君と廊下を歩いていると,突然「せんせい,Aちゃんってやさしいの?」と尋ねられました。それまで自分の気持ちを学校で積極的に表現することが少なかったB君からの突然の問いかけに,よい返事が思いつかず「B君はどう思う?」と尋ね返しました。すると「ぼく,Aちゃんはやさしいなぁっておもうんだ」と真剣な表情で前を向いて答えました。私はB君の心根を表すようなまっすぐなまなざしに感動し,すかさず「先生もそう思うよ。Aちゃんってやさしいよね」と言いました。するとB君は私の顔を見てにっこりと笑い,「おんなじだね」と言いました。
初任で聾学校の教員になってから,そのほとんどの時間を聴覚障害がある子どもたちと過ごしてきました。数年小学部に所属した以降は,幼稚部で3歳児から5歳児までの子どもたちと日々楽しくにぎやかに過ごしています。聾学校に通う子どもたちの多くは先天的に聴覚障害があり,乳幼児期からの言葉の発達が遅れ,自分の考えや気持ちを言い表すことに難しさを抱えやすくなります。そのため,聾学校幼稚部では,幼い子どもたちやそのご家族に専門的な支援を細やかに行います。聴覚障害のある子どもたちに人と伝え合い,わかり合う喜びを感じてほしいという願いのもと,幼稚部での勤務を続けてきました。幼稚部を担当したばかりの頃の私はうまくいかないことが多く,子どもたちとの関わりに悩み,大学院での学び直しを決めました。心理学に出会ったのはその頃です。
子どもの思いに沿ったコミュニケーションを通じて言葉や心の育ちを促すため,関係発達の視点[1]から考えるようになりました。子どもとの関わりをエピソード記述から見直し始めると,それまで見えていたものが,違う様相で見え始めました。それまでは,教え導く対象として子どもを見るあまり,関わりに教師側の指導意図が強く働き,一方向的な関係になりがちでした。そこには,「子どもに力を」という意識が働き,主体を教師である自分に置いた心の動きがありました。そのため,子どもの思いを受け止めようとしながらも,子どもからの発信に気づけず,わかったつもりになり,結果,その思いに沿わない関わりをしていたと思います。
教師としての自分の在り方に葛藤を抱え,関係発達に関する書籍を読むうちに,子どもを何者かにしようとするのでなく,今目の前にいる子どもをそのままで受け止めようとする方が,その子らしい成長が促せると思うようになり,実践に生かすようにしました。それは教師としての正義感や使命感を傍らに置き,目線を子どもに合わせるような作業だったと思います。子どもの多様な姿を受け止めながら,時と場を共にするうち,ある時その子の内にある芽が大きく伸び,思いもよらなかった色の花が開く瞬間に立ち会えるのです。B君がどうしてAちゃんをやさしいと思ったのか,その詳しい理由はわかりませんが,普段学校で自分の気持ちを口にすることが少なかったB君が,その心の内を真剣なまなざしで私に伝え,さらに共感を求めた姿に,私は成長の芽生えを見ました。
もし立ち会えなかったとしても,それはそれでいいのでしょう。その瞬間に偶然いられることがあるということが,この仕事をする上で最高の幸せだと思うようになりました。今後もたくさんの子どもと出会い,迷い,悩みながら心理学とともにまなざしの在り方を模索し,成長の芽生えに立ち会える瞬間を楽しみにしていきたいと思います。
文献
- 1.鯨岡峻(2006)ひとがひとをわかるということ:間主観性と相互主体性.ミネルヴァ書房
PDFをダウンロード
1