- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 111号 臨床心理の現場から――公認心理師誕生後のいまとこれから
- 大きなデータからひとりの子どもの支援を考えるには?
【小特集】
大きなデータからひとりの子どもの支援を考えるには?
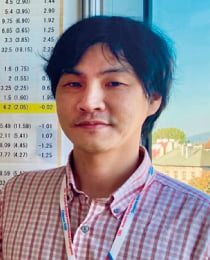
片桐 正敏(かたぎり まさとし)
Profile─片桐 正敏
北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。公認心理師,臨床発達心理士,特別支援教育士SV。専門は障害のある子どもの発達支援と認知・神経学的研究。Bayley-Ⅲ刊行委員。
Evidence Based Practice (EBP)
私自身,ちょっとめずらしいタイプの研究者だと思っています。「あなたの専門は?」と尋ねられると,発達心理学なのか,臨床心理学なのか,認知心理学なのか特別支援教育なのかうまく答えられません。おそらくこれらの領域の研究者たちから見たら,私はどの領域にも当てはまらないかもしれません。
私自身では,心理学者だと思っていますが,心理の実践家でありたいと思いますし,子どもの発達について研究しているつもりでもいますし,大学では特別支援教育を教えています。生理指標を用いた実験研究から事例研究まで幅広く行いますし,相談活動や専門家へのコンサルテーションもやります。何でも屋といえば何でも屋です。
今まで発達検査の標準化やコホート研究などを通して,たくさんの人のデータに触れてきた一方で,実践もしてきました。これらは私自身の中で断絶しているわけではなく,「証拠に基づいた実践(EBP)」という視点から考えると密接に関係があります。データによって裏打ちされた方法論や複数の実践的アプローチによるデータは,それらを直接援助対象者に適用する際には注意が必要です。平均値で比較する研究の場合,個々人の特徴がつぶれてしまった結果を見ています。
例えば「自閉スペクトラム症では局所から広域への注意の切り替えが難しい」[1]という結果は,自閉スペクトラム症の特徴を示す事象の一つであり,いくつかの側面において自閉スペクトラム症の人たちの行動面を説明することができます。しかし実際にあなたがかかわっている自閉スペクトラム症の人は,必ずしも目の前の事象をこの結果で説明できないかもしれません。臨床場面では,自閉スペクトラム症の特性として理解しつつも,個々人の特徴を十分考慮したうえで,目の前の事象をどう考えればよいか,という視点がとても重要になってきます。
Bayley-III発達検査
私は,Bayley-Ⅲ発達検査(以下,Bayley-Ⅲ)の標準化の仕事にかかわり,コロナ禍という災害を経てようやく2023年に日本文化科学社より出版することができました。発達検査の標準化には,たくさんの子どもの検査データが必要です。何万人というデータを集められればよいのですが,そうなると相当時間がかかりますし,何よりとてつもなく費用がかかります。多くの人にご協力をいただきながらなんとか必要な数(およそ1000名弱)を集めることができ完成させました。
Bayley-Ⅲは対面で子どもに実施する直接検査です(図1)。加えて,社会-情動尺度や適応行動尺度が付属しており,認知・言語・運動面の発達だけではなく,従来の直接検査ではみることができなかった発達の幅広い側面を包括的に評価することができる検査です。発達検査の標準化は本当に手間暇がかかります。特に日本には旧版が存在しない新しい検査ですので,この発達検査になじみのある人がいません。そこで,たくさんの人にテスターをやっていただくために,全国各地でテスター研修会を行い,研修会修了者に標準化データを取ってもらいました。もちろん私もデータを取りました。「赤ちゃんから高齢者まで発達検査,知能検査をとったことがある」というのが,私のちょっとした自慢です。

標準化について少し説明します。年齢・性別・地域・社会経済的背景などを考慮し,層化抽出法により全国から代表性を持つよう抽出された人たちに対して,データをもとに尺度を整え基準値を作成(ノルム化)します。この基準値は標準値とも言われ,標準化標本から得られた平均値を100とする相対的な位置を示す値です。例えば知能指数で言うと100が標準値であり,私たちの知能の平均を指します。こうすることでその人の知能の相対的な位置がわかります。
標準化は,そのサンプル数が多いほど信頼性が高くなるのですが,何万人のデータを集めるのは現実的ではありません。加えて,完全に無作為抽出された調査協力者かといえば,厳密には層化抽出法(地域や性別比が母集団と同じ比率になるよう事前に層を設定)や縁故法(標準化参加者に新たに参加者を紹介してもらう)など非確率抽出法と呼ばれる方法も駆使してデータを収集せざるを得ません。
こうして得られたデータは,もともと標準化していた欧米のデータと比較照合し,大きな乖離はないか検討します。加えて,日本にある他の発達検査を同時実施して検討することで,Bayley-Ⅲの妥当性を評価する,といった手続きで慎重に基準値の作成を行います。本来はもう少し早く出版する予定だったのですが,大詰めの段階で新型コロナウイルスが世界を席巻してしまいました。標準化作業もストップし,発売元の出版社とのやりとりも滞り,実に標準化作業から10年以上を要するという事態になったのでした。
コホート研究
コホート研究とは,ある特性を持つ集団(コホート)を長期間にわたって追跡し,特定の要因同士の関連を調べる疫学研究を指します。私は浜松医科大学に在職していた際に,中京大学の辻井正次先生の研究グループに所属して,学校コホートデータの収集と分析も行いました。学校コホート研究とは,文字通り学校に通学する子どもとその親を対象として長期間調査を行なう研究です。私はデータの収集を行い分析は同じグループに所属していた現お茶の水女子大学の伊藤大幸先生が担当していました。現在も続いているこのコホートは,何年も縦断的に追い続けている貴重なコホートデータなのですが,集めたデータは教育委員会や学校と共有し,結果をお返ししています。こちらも本当に時間と労力がかかるデータ収集ですが,得られた成果を確実に現場にお返しするという姿勢は本当にすばらしく,それだからこそ長らく現場との信頼関係を維持できてきたのではないかと思います。
心理学的にも意味があり,かつたくさんのデータを集める,というのには,それ相応の努力や工夫が必要になります。発達検査の標準化も学校コホートもさまざまな努力,そしてお金が必要です。
大きなデータと一人のデータを扱うということ
発達検査やコホートからの結果は,それ自体多くのデータを基にしています。支援を行う臨床家は,これらの結果を目の前の子どもに当てはめていくわけですが,当然齟齬が出てきます。ノルム化された発達検査や知能検査であれば,統計的に稀な開き(ディスクレパンシー)として示されます。コホートデータで示された結果では,それらの結果と目の前の子どもの状態像は異なっていることはよくあるでしょう。大規模データから得られたエビデンスは,あくまでも一般的な傾向を示しているかもしれませんし,時として日頃臨床を行なっていて十分うなずける根拠を示してくれることがあります。ですが,実際に生活をしている一人の人間すべてに適応できるものではなく,あくまでも相対的な位置を知る手がかりの一つにすぎません。
発達検査の開発にかかわり,実際に多くの子どもなどに発達検査や知能検査を行ってきた経験から言えることは,行動観察の重要性です。こうした標準化された検査は,数値を出すだけでしたら,臨床発達支援という視点で考えるとやる意味はあまりありません。検査中の応答の仕方や仕草,行動などは,検査結果の解釈を行う際に重要な手掛かりとなることがあります。標準値があるフォーマルアセスメントに加えて,行動観察などで得られるインフォーマルアセスメントを組み合わせた「包括的アセスメント」は,集団の中の個人の位置とその個人の特性双方を考慮し,どう支援に結び付けていくか,という考えが基盤にあります[2]。
若い先生方に期待したいのは,日頃子どもたちとかかわって感じた肌感覚(時には信念であったり違和感であったり)を大事にし,その感覚をデータとして示していくこと,そして得られた結果について,もう一度丁寧に子どもの観察を行ない,かかわりの中で子どもの姿を一人ひとり描き出してほしいということです。非常に曖昧な言い回しですが,データだけでは子どもの真の姿を見ることはできないでしょうし,行動の観察だけでは,その子どもの一つの側面しか見ることができないのです。
文献
- 1.Katagiri, M. et al. (2013) J Autism Dev Disord, 43, 395–403.
- 2.萩原拓 (2021) 発達障害支援につなげる包括的アセスメント. 金子書房
- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。
PDFをダウンロード
1




