にしんの学校
平石 界
ずいぶん前のことですが,札幌の某ゼミでボコボコにされた心を癒やすべく,寿司でも奮発しちゃおうかと小樽まで足を延ばしたときのことです。どの店に入ろうかとウロウロしていたところ,前からやってきた人が「そこの店がお勧め! まじうまいから!」と教えてくれたのです。旅先での交流に芽生え始めた北の大地への恐怖が和らぐ思いがしたものです。
昔話を思い出したのもニシンの論文を読んだからでしょう(Slotte et al., 2025)。かつては鰊御殿が建つほど北海道沿岸に押し寄せていた大群が姿を消してはや幾年。乱獲だけが原因と言えるのか,必ずしもはっきりしないようです。件の論文の対象であるところの大西洋のニシン群についても,長年の産卵場から急に姿を消したと思ったら,実は800キロも北で卵を生んでいたそうな。その原因というのがふるっていて,ニシンの集団記憶喪失のせいだと言うのです。盛っているのではなくて論文のタイトルそのまま。曰く,
Herring spawned poleward following fishery-induced collective memory loss ─漁業による集団記憶喪失でニシンの産卵地が北極の方に移動したよ─
これがもう,20万匹のニシンにタグを付けて追跡したとか,700億匹のニシンをスキャンしたとか,いろいろ圧倒的な研究だったんですが,個人的に一番衝撃だったのがニシンの回遊は文化であるとの記述。最初は「そりゃまた大げさな」と思ったのですが,読むにつれ,なるほどこれは文化かも。
説明しましょう。ニシンは回遊魚で,春になると越冬海域から産卵場へと移動する。南下して産卵した方が稚魚のためには好ましいのだけれども,それには海流に逆らって泳ぐ必要があり,体が小さい若魚にはつらいものがある。それでも通常は年長魚の群れ(school)に混ざることで南下するようになるそうです。ところが2016年生まれの魚が産卵年齢(4歳)に達した2020年ごろから南下するニシンが減ってきて,ここ数年はさっぱりいなくなってしまった。それは文化の断絶ゆえだというのです。
背景には国際的な漁獲量交渉の不調で2017年から2022年にかけてニシンを獲りすぎてしまったことがある。それも5歳以上の大きいニシンを狙って獲ったので,2016年魚が産卵に参加し始めたころに,手本となるべき”学校”の先輩がすっかり減ってしまっていた。そのせいで世代間の交流がうまく行かず,多勢を占める初心魚の「わざわざ南下しなくてもいいよね」という声が支配的になることで,南下産卵文化が途絶えてしまったのではないか。それどころか初心魚に混じって北で産卵し始めたベテランもいたそうで,情けないと言ったら言いすぎでしょうか(注)。
ヒト以外の動物の文化研究というと,チンパンジーの道具利用(Whiten et al., 1999)のような,手先や嘴(くち)先の器用さみたいな話ばかりを有難がってしまっていたので,この論文にはいささか虚をつかれた思いがしました。探してみると動物の「渡り」を文化とする見方はすっかり市民権を得ているようで(Aikens et al., 2022),中には北米の再移入ビッグホーン(野生ヒツジ)の渡りに累積的文化の兆候が見られるなんて文献まである(Jesmer et al., 2018)。己の不明を恥じるとはまさにこのことです。サボらず手広く読むこと大事ですね。
ところで件の小樽の寿司屋,同行の後輩から即座に「あんなのヤラセに決まってるじゃないですか。一般的信頼(山岸, 1998)が高すぎですよ」と窘(たしな)められ,事なきを得たのでした。ただ単に幅広く交流すればいいってもんじゃないのも,学校が常に快適な場所とは限らないのと同じで,難しいところですね。
Profile─ひらいし かい
東京大学大学院総合文化研究科博士課程退学。東京大学,京都大学,安田女子大学を経て,2015年4月より慶應義塾大学。博士(学術)。専門は進化心理学。
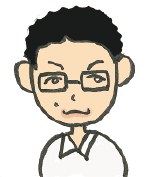
- (注)言うまでもありませんが,めちゃくちゃ意訳してます。
PDFをダウンロード
1





