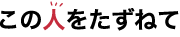石川 信一(いしかわ しんいち)
Profile─石川 信一
博士(臨床心理学)。臨床心理士,公認心理師。宮崎大学教育文化学部専任講師,同志社大学心理学部准教授,スワスモア大学フルブライト研究員,マッコリー大学・トゥルク大学客員教授などを経て,2018年より現職。専門は臨床児童心理学。単著に『不安で学級に入れない子がちょっぴりウキウキを見つけるために…教室の中の認知行動療法:問題解決のステップを学ぼう』(明治図書出版),『イラストでわかる子どもの認知行動療法:困ったときの解決スキル36』(合同出版)など。
石川 信一氏へのインタビュー
─これまで取り組んできた児童や生徒を対象とした研究や実践について教えてください。
主なテーマの一つは,子どもの不安症に対する認知行動療法です。1990年代半ばから,子どもの不安症に対する認知行動療法の有効性を示す研究が次々と発表され,私もこの分野に貢献したいと考えるようになりました。しかし,当時の日本では,子どもに対する認知行動療法の実践はほとんど行われていませんでした。そこで私は関連書籍やワークショップを通じて学び,プログラムを自ら作成し,実践してきました。特にRCT(ランダム化比較試験)は国際的な評価を得るうえでも大きな目標でした。当時の日本では,子どもを対象としたRCTの実施例が少なかったのですが,同志社大学に移ってから心理臨床センターでRCTを実施する機会に恵まれました。実施には多くの困難が伴いましたが,2019年には,日本においても子どもの不安症に対する認知行動療法の有効性を示す研究を発表することができました。
もう一つのテーマは,学校現場における集団を対象としたユニバーサル介入です。ユニバーサル介入とは,リスク状態にかかわらず,すべての児童生徒を対象とする介入方法のことです。たとえば,学級で実施する場合は,学級に所属する児童生徒全員が参加できる形式で実施します。最初に勤務した宮崎大学の教育文化学部(現在は教育学部)では,ソーシャルスキルトレーニングの第一人者の佐藤正二先生と佐藤容子先生がいらっしゃり,その実践に関わる機会をいただきました。そこでは,学校の先生に認知行動療法の技法を伝え,それを授業の中で実施していただくという形で,実践に取り組んでいました。当初はソーシャルスキルの向上を目指していましたが,その不足が抑うつのリスク要因であるという知見を踏まえ,予防的アプローチの集団プログラム開発に取り組みました。同志社大学に移ってからは他の先生と連携し,「こころあっぷタイム」という包括的な予防プログラムを開発しました。現在はその社会実装に向けた取り組みも進めています。
─研究と実践を両立することの難しさ,そして,それをどのように乗り越えてきたか教えてください。
研究と実践の両立には時間と手間がかかり,どちらも簡単には評価されません。それでも続けてこられたのは,仲間の存在があったからです。悩みを共有したり,一緒に考えたり,そういった「支え合い」が大きな力になりました。研究には浮き沈みがありますが,それを共に乗り越えてくれる仲間の存在は,私にとって何よりの支えでした。
あと,今でも大切にしているアドバイスがあります。ある先生から「実践研究においては継続が何より重要だ。まずは10年続けてみなさい」という助言をいただいたことが,今も心に残っています。努力と継続によって専門性は積み上がっていく。その言葉を支えに,これまで歩んできたように思います。特別な「乗り越え方」があるというより,「続ける」ことを習慣にする。これが自分にとってのコツなのだと思います。
─これから挑戦していきたい研究や実践について教えてください。
実は現在,進むべき方向について模索しているところです。近年はテクノロジーの発展が著しく,学際的な視点や他分野との連携が不可欠になりつつあります。それはとても刺激的で,私自身もそうした研究に取り組んでいきたいと考えています。一方で,「これまで自分が掲げてきた目標は果たしてどれだけ達成できているのか」と自問することも増えてきました。たとえば,「認知行動療法を受けられる子どもが増えたか」「学校現場でメンタルヘルスに関する予防的介入がカリキュラムとして本当に根付いているか」といった点について考えると,まだ道半ばであると感じています。新たなテーマに挑戦すべきか,これまでの取り組みをさらに深めるべきか,その狭間で思い悩んでいるところです。
ただ一つ明確にあるのは,「日本の実践をもっと世界に発信したい」という思いです。日本特有の文化や制度のもとで,どのようなメンタルヘルス支援や教育実践が行われているかという点には,国際的にも関心が高まっています。たとえば,担任の先生が非常に多くの役割を担っているという点は日本ならではの特徴です。その構造のおかげで,ユニバーサル介入のようなアプローチが,実は日本では比較的うまく機能する余地があるのではと感じています。欧米では,近年ユニバーサル介入の効果に限界があるという議論も聞かれますが,日本の文脈ではむしろ適合しやすい面もあるのではないでしょうか。
もう一つ取り組みたいのは,より緻密な研究です。たとえば,認知行動療法のセッション中に交わされる言葉の量や内容を分析し,その特徴を明らかにしたうえで,海外との比較を行いたいと考えています。そうした緻密な分析を通して,「日本にはこうした見方やアプローチがあるのだ」と世界の研究者に伝わるような研究を目指していきたいと考えています。単に欧米のやり方を追うのではなく,日本だからこそ捉えられる現象,日本でしか見えない課題を丹念に掘り下げて,世界に新たな視点を発信したいと考えています。
─若手研究者に向けた熱いメッセージをお願いします。
今の若手研究者の皆さんは,本当に忙しい日々を送っていると思います。最近は,苦しそうな表情をしている若手研究者を見かけることもあります。でもやっぱり研究は楽しくないと続かないし,苦しいだけでは持たないですよね。だからこそ,「研究を楽しんでほしい」と強く思っています。もちろん,私たちの世代にも苦しい時期はありましたが,それでも仲間と一緒に研究したこと,時には笑えるようなエピソードがあったことは,何よりの支えになってきました。一緒に笑い合える仲間と出会えることも,研究の大きな魅力の一つですよね。また,研究仲間に限らず,学校の先生や保護者の方など,さまざまな人たちと連携して,自分の輪を広げていってほしいですね。
それともう一つ,「自分はどんなことを発信できるのか」を考えながら,ぜひ新しいことに積極的に挑戦してほしいです。今の若手研究者はとても素直で,先輩や指導教員の話をよく聞いてくれます。しかし,それだけでは新たなイノベーションは生まれにくいものです。若手だからこそ持てる視点が,学問に新たな風を吹き込むはずです。遠慮せず,あなたならではの視点や意見をぜひ積極的に発信してください。私はそういう姿勢を心から応援しています。
聞き手はこの人
インタビューを終えて
現場に根ざして研究を続けてこられた石川先生のお話には,深く共感する点が数多くありました。「現場に足を運ぶこと」について,私も子どもを対象とした研究に取り組む中で,幼稚園や小学校に足を運び,子どもや先生,保護者の方々と直接関わることを大切にしてきました。また,子どもたちのために先生や保護者の方々と一緒に夏祭りで焼きそばを作ったり,ドッジボール大会で審判を務めたりと,研究者という立場を超えた関わりも信頼関係を築く土台になっていると感じています。「仲間を大切にすること」も私が大事にしてきた姿勢の一つです。私は特定の領域にとらわれず,さまざまな学会や研究会に参加し,人とのつながりを築いてきました。そうして出会った仲間と今では共同研究を行うようになり,対話や協働を通じて,一人では実現できなかった研究が形になることに日々喜びを感じています。「継続すること」も私にとって欠かせない信念です。続けられない理由を探すのではなく,続ける理由を見つけること。その姿勢の大切さを教えてくださった先生が私にもいます。さまざまな制約がある中でも,自分なりの意味や楽しさを見いだして取り組みを続けることが,専門性を深める力になると実感しています。
Profile─おぐに りゅうじ
就実大学心理学部心理学科講師。博士(心理学)。専門は社会心理学,発達心理学。立命館大学総合心理学部特任助教を経て現職。筆頭論文にGratitude promotes prosocial behavior even in uncertain situation. Scientific Reports, 2024, https://doi.org/10.1038/s41598-024-65460-zなど。

PDFをダウンロード
1