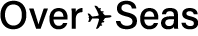- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 111号 臨床心理の現場から――公認心理師誕生後のいまとこれから
- 英国でのマインドフルネス修行
英国でのマインドフルネス修行

芦谷 道子(あしたに みちこ)
Profile─芦谷 道子
博士(医学)。公認心理師,臨床心理士。米国Global Mindfulness Collaborative(GMC)認定 MBSR(マインドフルネスストレス低減法)指導者。筆頭論文に「高校生を対象としたマインドフルネス・プログラム.b(ドットビー)の主観・生体指標による効果評価」教育心理学研究, 72, 121–132, 2024,など。
本稿では,私がマインドフルネスを学ぶ過程で生まれた英国との絆についてご紹介したいと思います。留学とは異なる形での海外体験として,皆様のご参考になれば幸いです。
心理士および教員養成大学の教員として,長年にわたり子どもの心理療法や教育に携わってきた私は,子どもたちの自己存在を支え,ウェルビーイングを育む心理教育的アプローチを模索していました。そんな折,医師の伊藤靖先生より,英国の教育団体 MiSP(Mindfulness in Schools Project)が開発した子ども向けのマインドフルネス・プログラム「.b(ドットビー)」をご紹介いただく機会を得ました。ポジティブな側面もネガティブな側面も,すべてを優しく,慈しみをもって受け入れるマインドフルネスの姿勢は,まさに私が探し求めていたものであり,「このプログラムを子どもたちに届けたい」と強く思いました。こうして私の英国におけるマインドフルネス修行,そして英国との連携による子どもマインドフルネス・プロジェクトが始まったのです。
2019年に初めて渡英し,「Teach .b(ティーチ・ドットビー)」という講師養成プログラムに参加しました。歴史ある石造りの建築物と現代的なデザインが美しく調和するロンドンの街並み,花々で彩られた出窓,祈りの息づく教会――その凛としつつも温かな雰囲気の中でマインドフルネスを学べることは,大いなる恵みの体験でした。ティーチ・ドットビーには,ヨーロッパ各地からマインドフルネスを学ぼうとする志ある教育関係者(多くは教師や心理士)が集まり,参加者は,実践を交えながらマインドフルネスの教育的可能性や課題について熱く議論を交わしました。英国では心の健康教育が重視され,マインドフルネスの学びが学校教育に組み込まれている地域もあると知り,日本との違いに驚かされました。
その後,講師養成の指導資格を得るために短期の渡英を重ね(コロナ禍ではオンラインに切り替えられることもありました),ティーチ・ドットビーのアシスタントとして研鑽を積み,伊藤先生らとともに MiSP日本支部を立ち上げました。そして,ドットビーの教材(テキストやスライド)の翻訳やビデオの吹き替えにも取り組み,日本で講師を育成する体制を整えました。幸いにも日本学術振興会や民間企業の助成金を得ることができ,オックスフォード大学のウィリアム・カイケン教授の協力を得ながら,日本における子どもマインドフルネスの効果を検証するプロジェクトも開始しました。
さらに2023年には,MBCT(マインドフルネス認知療法)を開発された マーク・ウィリアムズ教授の最新プログラム「フレーム・バイ・フレーム」を学ぶため,ウェールズ地方にあるバンガー大学も訪れました。そこは大都会のロンドンとは対照的な,まるでおとぎ話に出てくるような愛らしい大学町で,小高い丘の上にある自然に包まれた大学施設に,世界中からマインドフルネスを志す人々が集まっていました。私たちはソーシャルメディアから離れ,沈黙の中で瞑想を続けるサイレント・リトリートの日々を過ごしました。坐布を並べて静かに座り,柔らかな芝生の上を裸足で歩く歩行瞑想,木陰に横たわり小鳥のさえずりに耳を澄ませながらのボディスキャンなどに身を浸しました。滋味深くおいしいランチや飲み物,デザートが毎日ふんだんに用意されており,目が合えば柔らかな笑顔で互いを迎え合いました。そこには,静けさと調和,多様性への祝福と歓待が満ちており,それは,自分の心と身体,魂が優しく開かれていくような,驚きにあふれた体験でした。
こうしてマインドフルネス修行の場として訪れた英国は,私にとってマインドフルネスの“故郷”のような存在となりました。そこで得た平和で慈しみにあふれたウェルビーイングの体験を日本へ持ち帰り,ろうそくの火を手渡すように子どもたちに届けたい。その思いが,私の現在の研究や実践の原動力となっています。
PDFをダウンロード
1