- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 100号 「弱み」を「強み」に変える心理学
- 「弱み」を「強み」に変える心理学
【特集】
「弱み」を「強み」に変える心理学
2022年2月の北京オリンピック。日本女子カーリングチームのメンバーは決勝戦に臨むにあたり,わざわざ自分たちのミスや苦戦した試合などの弱点を引き合いに出し,「ミスや接戦をたくさん経験できたことは,むしろ決勝戦ではアドバンテージになる」と言いました。このように「弱み」だと思い込んでいたことが,見方や考え方を変えるだけで「強み」になることがあります。
今回取り上げる「弱み」とは,一般的に言われるような社会的弱者や心身の障害の問題だけを指すのではありません。誰もが日ごろから感じている苦手意識や劣等感,コンプレックスなども含みます。このような,「弱み」を包み隠さずむしろ利用することで「強み」に変えて,個々人の思考や認識,人と人のコミュニケーション,社会システムなどをポジティブな方向へ変えようとする考え方が,心理学やその近接領域で広がっています。では,どのように「弱み」を「強み」に変えるのでしょうか,またその結果,何がもたらされるのでしょうか。具体的な研究や事例報告を見ていきながら,あなた自身にとっての「弱み」を「強み」に変えるヒントを探してください。(坂田陽子)
〈弱いロボット〉的思考のすすめ
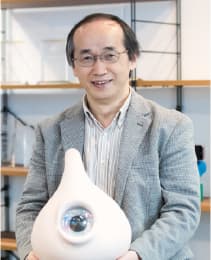
岡田 美智男(おかだ みちお)
Profile─岡田 美智男
東北大学大学院工学研究科情報工学専攻博士後期課程修了。工学博士。専門は社会的ロボティクス,認知科学。NTT基礎研究所情報科学研究部,国際電気通信基礎技術研究所(ATR)などを経て2006年より現職。単著に『ロボット:共生に向けたインタラクション』(東京大学出版会),『〈弱いロボット〉の思考:わたし・身体・コミュニケーション』(講談社),『弱いロボット』(医学書院)など。
はじめに
本特集のテーマにある,「弱み」を「強み」に変えるとは,どのようなことか。本稿では,筆者らが〈弱いロボット〉の研究を進める中で議論してきたことを記してみたい。
はじめに,身近な道具である〈ハサミ〉と私たちとの関わりについて考えよう。ハサミは机の上に置かれたままでは,本来の機能を発揮できない。私たちの手の中にあって,紙を切る,糸を断つなどの機能が立ち現れる。その意味で,ハサミに内在する「弱さ」は私たちの手の働きを必要とし,その自在に動く手がハサミの「弱さ」を補っている。
一方の私たちの手はどうだろう。その柔らかな手では,堅い紐を断つことはできない。手の柔らかさ(弱さ)は,ハサミの硬い鋼の手助けを必要とし,そこでハサミの「強み」を引き出している。このとき私たちの手の柔らかさはハサミを使いこなす上では「強み」となっていることに注意したい。ハサミの「弱さ」は私たちの手に備わる「弱さ」を「強み」に変え,それを引き出しているようなのである。
このように素朴な道具と私たちとの関わりでは,お互いに「弱さ」を抱えつつも,その協働によって,とても「しなやかなシステム」を作り上げる。このとき,お互いの「弱さ」は消えて,もはや見えないけれど,それぞれの個に備わる「弱さ」はしなやかな関係性を生み出す「のりしろ」として,その背後でしっかりと機能していることだろう。
身体と環境とが〈ひとつのシステム〉を作る
同様の図式は,私たち(あるいはロボット)の身体とそれを取り囲む環境との関わりに見ることができる。ニコライ・ベルンシュタインが指摘するように,ヒトは進化の過程で,しなやかな体幹と多様な動作を生み出す体肢を手に入れ,生態系の中で高度に適応し生き延びてきた[1]。一方,この柔軟性や多様性と引き換えに,「自らの身体を統制する際に必要な数百から数千のオーダーの冗長な自由度をどのように克服するのか」との課題(ベルンシュタイン問題)をあわせ持つことに。生まれたばかりの乳児が床を背にしてただ手足をバタバタと動かすように,「自らの中で抱えきれない冗長な自由度をどのように律したらいいのか」というわけである。
その解の一つとして見出されたのは,自らでは律しきれない身体(「弱さ」)をまわりの環境に半ば委ねつつ,冗長な自由度の一部を制約してもらうことで,そこで「しなやかなシステム」(協応構造)を作ろうとする方略であった。
例えば,地面の上を歩き続けるために,私たちがしていることはどのようなことか。容易に思い浮かぶのは,片方の足にしっかりと重心を置いた上で,もう片方の足をそっと前に進めてみるもの。その足が地面に接したのを見計らい,重心をその前足へと移していく。これを繰り返せば,なんとか「歩く」行為は完成するはずだ。
ところが片方の足を前に進めようとするとき,もう片方の足はほぼ一本足の状態になってしまう。そこで自らの身体の揺れに気を配りながら,そうっと行う。これでは,なんとも頼りなく非効率なものだろう。かつてのロボットの歩行パターン(静歩行モード)は,とてもキカイキカイした,ぎこちないものだった。自らの責任の範囲だけで歩こうとすると,不安定で脆弱なものになってしまうのである。
このところの二足歩行ロボットでは,そうしたイメージはもうない。ホンダの〈アシモ〉にあっては,軽くステップを踏み,小走りもする。どのような飛躍があったのか。試行錯誤を経て見出されたのは,「自分の力だけでなんとか……」とのこだわりを捨てて,むしろ「地面を味方につけてしまおう!」との方略への転換だった。
なにげなく一歩を踏み出そうとするとき,わずかに勢い余って,重心は足底(支持基底面と呼ばれる)からわずかに外れてしまう。少し前のめりになって倒れ込む感じだろう。自らの制御を一瞬だけ放棄してみると,その踏み出した一歩はたまたま地面からの反力の助けを借りて,どうにかバランスを維持できた。これを繰り返してみたら,地面に対する〈委ね〉と地面からの〈支え〉との動的なカップリングが生まれ,結果として,しなやかで軽快な歩行モード(動歩行モード)を見出したというわけである。
〈弱いロボット〉とその関係論的な行為方略
これまで筆者らは,他者の手助けを上手に引き出しながら,結果として合目的的な行為を組織するような,関係論的な行為方略を備えたロボット(〈弱いロボット〉)の研究を進めてきた。その一つは,自らではゴミを拾えないものの,まわりの子どもたちの手助けを上手に引き出し,結果としてゴミを拾い集めてしまう〈ゴミ箱ロボット〉である(図1)。

このロボットは自らではゴミを拾えない「弱さ」を抱えつつも,それを隠すことなく広場の中をヨタヨタと歩きまわる。それを眺めていた子どもたちは,「あっ,ゴミを拾い集めたいのかな……」と気持ちを汲むようにして,あたりからゴミを探しだしてきてくれるのである。
そのベースにあるのは,〈ゴミ箱ロボット〉のヨタヨタした動き(biological motion),志向性や社会性の表示,くわえて「ゴミを拾うにも拾えない」という機能の不完全さだろう。子どもたちの志向的な構えを引き出すことに貢献しており,思わずロボットの行動の先回りをして手助けしようとしてしまう。一方のロボットは,子どもたちを味方につけつつ,一緒になって「しなやかなシステム」を作り上げるのである。
初期段階では〈ゴミ箱ロボット〉の他者を味方につけながら目的を果たしてしまう関係論的な行為方略や社会的なスキルに着目していた。しかしフィールドワークを進めてみると,子どもたちの表情はどこか満足気であり,生き生きしていることに気づいた。〈ゴミ箱ロボット〉の「弱さ」は,子どもたちの優しさや「強み」を引き出すとともに,「自らの能力が十分に生かされ,生き生きとした幸せな状態」(ウェルビーイング)を向上させるようなのである。
リチャード・ライアンとエドワード・デシらの自己決定理論[2]によれば,ウェルビーイング を支える要素として,自律性,有能感,関係性などの要素をあげている。〈ゴミ箱ロボット〉に当てはめるなら,子どもたちはゴミを拾うことを強いられてはおらず,手伝うかどうかは子どもたちに委ねられている(自律性の担保)。くわえて〈ゴミ箱ロボット〉の手助けとなれたことに対する有能感や達成感もある。もう一つは,〈ゴミ箱ロボット〉や他の子どもたちと一緒に貢献しあえていることの喜びもあるだろう(関係性やつながり感)。
子どもたちの中で「ロボットのために,ゴミを拾ってあげる」という利他的な気持ちがどこまで働いているかはわからない。ただ,その姿からは〈利他〉を超えて,「私たち(we)」として〈ひとつのシステム〉( we-mode)を作り出しているようなのである。
人とロボットとの社会的相互行為の組織化
次に〈弱いロボット〉の一つ,街角などでモジモジしながらティッシュを配ろうとする〈アイ・ボーンズ〉の振る舞いを見てみたい(図2)

ティッシュを配ろうとする相手は,そこを行き交う見知らぬ他者であり,このロボットも多くの人にとっては素性のわからない存在である。ティッシュを差し出そうとするも,相手が受け取ってくれなければ手渡すことにならない。「対面的な相互行為には賭けを伴う」との指摘にあるように,これも脆弱なものだろう。双方は相手に半ば委ねる必要もあり,お互いにゴールを共有できていないとうまくいかない。
人の動きというのは殊のほか俊敏であり,なかなかタイミングが合わない。目の前に人が現れるたびにそっと差し出してみては,うまくいかないとわかると残念そうに手を引っ込めることを繰り返す。その姿はどこかモジモジしているようにも映る。ただ,そんな様子をかわいそうに思ってか,一人のおばあちゃんがそこに立ち止まってくれた。ロボットの手の動きに合わせるようにして,ティッシュをうれしそうに受け取ってくれたのである。
ティッシュを受け渡しする際には,わずかだけれど「心を一つにする」瞬間がある。ゴールを共有し,タイミングを調整しあう。おばあちゃんがうれしそうにしているのは,ロボットとの受け渡しがうまくいったことの達成感や一体感など,それらが複合したものだろう。ここでも,ウェルビーイングな状態を生み出しているようなのである。
言葉足らずな発話から生まれるもの
日常的な会話の場面ではどうだろうか。筆者らが着目しているのは,子どもたちの言葉足らずな発話である。子どもがうれしそうに,今日の楽しかった思い出をお母さんに伝えようとする場面を思い浮かべてみたい。
「きょうね,いっぱい遊んだ!」(えっ,だれと?),「そらちゃん」(へぇー,なにして遊んだの?),「おえかきした!」(あー,そうなんだ!),「ひなちゃんもいっしょ」(へぇー,たのしかった?),「うん」……。
どこか不完全で,言葉足らずなところもあるけれど,子どもは聞き手からの手助けや積極的な解釈を上手に引き出し,なんとかおしゃべりを続けてしまう。過不足なくしっかりと話せる子どもの発話と比べても,むしろ豊かなコミュニケーションを生み出すようなのである。
「きょうね,いっぱいあそんだ!」は,「楽しい出来事をひとまず伝えておこう」との思いが先走って,「その他のことは適当に解釈してくれるだろう」との期待もあってのことだろう。聞き手に対して半ば委ねていることもあって,つい引き込まれて「だれと遊んだのか」「どんなことをして遊んだのか」と矢継ぎ早に尋ねてしまう。そんな聞き手の関心や助け舟に支えられるように,「そらちゃんとあそんだ」「おえかきした」という情報が引き出されていく。
これは発話の不完全さ(「弱さ」)が聞き手からの積極的な関わりを引き出し,一緒になって「しなやかなシステム」を作り上げる構図そのものだろう。「きょうはね,そらちゃんとね,みんなでお絵描きして遊んだ」ことを一方的に伝えるはずの発話は,聞き手との協働の作業となっている。話し手の思いと聞き手の関心とが上手に絡まりあって,お互いの気持ちを共有しあうwe-modeの状態を作り上げるのである。
ここでベルンシュタインの指摘した「冗長な自由度を上手に切り盛りする」という観点を当てはめてもおもしろい。どこにフォーカスを絞り,どのようなことを言及したらいいのか。どのような文体を選ぶべきか。一つひとつ発話を繰り出す上でも,膨大な選択肢(自由度)が存在する。子どもの言葉足らずな発話は,自らの中で抱えきれない自由度を伴ったまま,聞き手に半ば委ねつつ,そこで自由度の一部を制約してもらっているとの解釈も可能だろう。聞き手(社会的環境)からの制約を利用しつつ,同時に聞き手の多様な関心に柔軟に適応させてしまう。つまり冗長な自由度(「弱さ」)を生かし,それを柔軟性や適応性(「強み」)に変えているのである。
人とロボットとの共同想起に向けて
上記の言葉足らずな発話様式を検討する中で生まれたのは,子どもたちに昔話を語り聞かせようとするも,時々大切な言葉をモノ忘れしてしまう〈トーキング・ボーンズ〉である(図3)

「むかしむかし,あるところ」,「おじいさんとおばーさんがいました」,「おじいさんは山に柴刈りに,おばーさんは川に……」,「えっと,なにをしに行ったんだっけ」,「えっとー」。
ロボットがモノ忘れするというのも妙な話だけれど,「あれっ……」,「えーと,なんだっけ?」などと困った仕草をすると,まわりの子どもたちは目を輝かせて,そこに関わろうとする。そして子どもたちからの「せんたくにいったんじゃないの?」との手助けに「あっ,それそれ! せんたくにいったんだった」とその続きを話し始める。
「すると川の中から,どんぶらこ,どんぶらこと……」,「あれっ,なにが流れてきたんだっけ?」,「スイカじゃなくて…えっと」。
〈トーキング・ボーンズ〉の頼りない語りに,子どもたちも身を乗りだして,なんとかロボットの助けになろうとする。「なにを困っているのか」,「なにを思い出そうとしているのか」と,ロボットの気持ちに寄り添うようにして,「ああでもない,こうでもない」と考えを巡らす。
ここで〈トーキング・ボーンズ〉が淡々と昔話を読み聞かせるだけなら,子どもたちはすぐに退屈してしまうことだろう。ロボット側の「不完全さ」(記憶や想起の不完全なところ)が子どもたちの積極的な関わりや「強み」を引き出している。一方で子どもたちであっても,昔話の『桃太郎』を最後まで諳んじることはできない。お互いの〈弱いところ〉を補いながら,その〈強み〉を引き出しあう〈ひとつのシステム〉を作り上げるのである。
子どもたちは手の掛かるロボットの世話をしながらも,どこかうれしそうにしている。こうした関わりは,「子どもたちがロボットの世話をしていたら,結果として自らも学んでいた」といった関係発達論[3]にもつながるものだろう。
まとめ
自らの中に閉じていては,「弱さ」は弱さでしかない。地面に委ねるように繰り出した一歩は,その地面を味方につけるようにして「しなやかなシステム」を作り上げる。本稿では,そうした「弱さ」を「強み」に変える〈弱いロボット〉の方略を紹介してみた。詳しくは,拙著『ロボット:共生に向けたインタラクション』(東京大学出版会)に譲ることとしたい。
文献
- 1.Bernstein, N. (1967) The Co-ordination and Regulation of Movements. Pergamon Press.
- 2.Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000) Am Psychol, 55, 68–78.
- 3.鯨岡峻 (1999) 関係発達論の構築.ミネルヴァ書房.
- *COI:本記事に関連して開示すべき利益相反はない。





