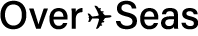- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 109号 アートは人と人の間で生まれる
- そこに行かなければならない理由
そこに行かなければならない理由

保子 英之(ほし ひでゆき)
Profile─保子 英之
ロンドン大学ユニヴァーシティカレッジ MSc in Cognitive Neuroscience 修了。ウィーン大学美術史研究所,マックスプランク経験美学研究所,株式会社リコーなどを経て2024年より現職。博士(医学)。専門は神経美学,脳磁計。共著論文にThe eye tracks the aesthetic appeal of sentences, Journal of Vision, 18(3), 19。
“Because of you.” 初めて対面した憧れの先生との面談で,なぜロンドンに来たのかと尋ねられて,乏しい英語ボキャブラリーの中から私がなんとかひねり出した言葉です。
2013年当時,私の専門とする「神経美学」はまだ学問として発展途上で(いまもまだそうかもしれません),腰を据えて研究ができるラボは,世界中どこを見てもロンドン大学のセミール・ゼキ教授のところ以外にはありませんでした。学部3年時にゼキ先生の著書を読んでピンと来てしまった私は,ロンドン大学への進学を決め,好きでも得意でもなかった英語を必死で勉強し,バイトを詰め込んで資金を貯め,どうにかマスターコースへの入学を決めました。それでもまだ,この先生のもとで研究ができると決まったわけではありません。指導教官になってくれるよう,お願いしに行って認めてもらわなければならないのです。
渡英して無事にコースに入学した私は,まず,先生のラボにいたポスドクの日本人に連絡をとって話を聞きました(後から聞くと,この方がいろいろと取り計らってくれたようで,ほんとうに感謝してもしきれません)。その情報をもとに,教授にメールでアポを取りました。「来週ラボに面談に来られますか?」。返事が来たときにはびっくりするとともに,一気に緊張が高まるのを感じました。ロンドンにすでに3か月ほど滞在していたとはいえ,まだ英語もつたなく,日々の生活で精いっぱいの私が,いっときの興味だけでいきなり知らない研究分野に飛び込んで(しかも理転),やっていけるのだろうか,迷惑をかけるんじゃないだろうか,そんなネガティブな気持ちが渦巻いているのを感じていました。しかし,就活の「し」の字も知らないままここまで来てしまった私に,もう退路はありません。腹をくくって教授との面談に行きました。
憧れの先生に初めて会ったときの,あの目はいまだに忘れられません。動物の電気生理研究で高名な先生は,私を見て,それこそまるで動物がとても興味深いなにかを見つけて,それをまじまじと眺めるときのような,小さな丸い瞳を優しくこちらに向けていたのでした。私はたどたどしい英語で,なんとか先生の質問に答えていきました。「どうしてロンドンに来たの?」という質問に困ってしまった私が,数秒の沈黙ののちに”Because of you.”と答えると,先生や同席していたラボメンバーたちは大声で笑いました。「ラボメンバーとして歓迎します」というメールが来たのは,その数日後のことでした。これが,生まれて初めて「夢がかなった」瞬間でした。
それから,私はこのラボで修士の学位を取得し,その後,また別の国に住処を移して研究を続けることになります。学部卒業の直後という,まだ身分も収入も不安定な時期に海外で暮らすことは,不安も大きく,リスクや危険も伴い,必ずしも良いことばかりではありません。30代半ばとなった私はいまでも,当時の貸与型奨学金の返済に苦しんでいます。それでも,たった5年間という短い期間でしたが,20代の多感な時期に欧州で暮らす経験ができたことは,研究者としても人間としても,何事にも代えがたい価値があったと感じます。
どこにも伝手がないまま渡英したことにはじまり,いま思い返すと,私は無鉄砲なことばかりしていました。こんな私でもどうにかなったのは,「ロンドンでないと自分のしたい研究ができない」という,そこにいなければならない明確な理由があったからだと思います。留学は,「アカデミアの道に進むから」という理由だけで,誰しもにお勧めできるものではありません。しかし,慣れ親しんだ煮物の味や,夜中のコンビニにシュークリームを買いに行ける便利さを捨ててでも,そこに行きたい理由や,行かないとかなえられない夢があるのならば,その強い気持ちだけでどんな困難も乗り越えていけるのではないでしょうか。
PDFをダウンロード
1