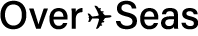- HOME
- 刊行物のご案内
- 心理学ワールド
- 111号 臨床心理の現場から――公認心理師誕生後のいまとこれから
- グローバル化の時代に死をどう悼むか
グローバル化の時代に死をどう悼むか

近藤(有田)恵(こんどう(ありた)めぐみ)
Profile─近藤(有田)恵
博士(人間・環境学)。専門は死生心理学・医療倫理学。大阪医科薬科大学准教授などを経て2025年より現職。筆頭論文に Changing funerals and their effects on bereavement grief in Japan. OMEGA - Journal of Death and Dying, 91(3), 1548–1560, 2023. https://doi.org/10.1177/00302228231158914 (Original work published 2025)
2024年4月から1年間,私はドイツ・ライプツィヒ大学のグローバルダイナミクス研究センターに研究員として滞在し,死生心理学の研究に取り組む機会を得ました。家族のサバティカルが先に決まり,当時の私の勤務先には休職制度がなく,一度はキャリアの継続を諦めかけていました。そうした折に,ライプツィヒ大学のHeé先生が手を差し伸べてくださったことにより,研究者としての歩みを続けることができました。研究者同士の夫婦にとって,双方のキャリアをどう継続していくかは大きな課題です。近年は,欧米を中心にカップル単位でのキャリア支援制度を整備する大学も増えてきており,その潮流に後押しされる形で私は渡独することができました。
ドイツの大学における研究者の働き方は非常に柔軟です。もちろん定められた業務はありますが,それ以外の時間については,各自が自律的に研究を進めています。そのため,職場から離れた地域に居住する研究者も多く,パリからドイツの大学に通勤している研究者もいました。私も,夫の職場がある旧西ドイツの首都・ボンで家族とともに暮らし,必要に応じて大学へ赴く形で研究を継続しました。ボンは私にとって思い出深い地でもあります。1990年から1年間,父の在外研究に帯同した当時は,ベルリンの壁が崩れた直後で,再統一への熱気と混乱が街に満ちていたことを記憶しています。今回,再びこの街に身を置き,社会や人々の価値観がどのように変容してきたかを肌で感じる日々でした。
とりわけ印象的だったのは,多様性への寛容な姿勢です。子どもが通ったインターナショナルスクールには40か国以上の児童が在籍し,異なる文化的背景をもつ人々と関わることが日常となっていました。このような環境の中では,服装や食事など身近なところから,多様な価値観を理解し尊重する姿勢が自然に育まれていきます。これは教育現場に限らず,死や喪といったセンシティブな領域にも深く影響を与えていると感じました。
今回の滞在では,宗教や文化の異なる社会における死者との関わりや葬送儀礼,そして悲嘆の過程を比較文化的に捉え直すことをテーマに研究を進めました。ドイツ社会では多宗教化・脱宗教化が進む中,国民の半数近くがいずれの宗教にも属していません。葬儀は形式よりも,故人の生前を偲び,つながりを感じることに重点が置かれ,少人数で簡素に行われるように変化してきています。私が特に注目したのは,葬儀の「個人化」が進む中で,喪の過程がどのように変化しているのかという点です。かつては地域や共同体によって支えられていた葬儀が,個人と家族単位の営みに変わりつつある今,自らの死をどう迎えるか,他者の死とどう向き合うかが,より強く個人に問われるようになっていると感じました。また,ドイツでは多文化・多宗教社会の進展に伴い,医療や葬送の現場でも文化的背景への配慮が求められており,スピリチュアルケアの専門職や多文化対応のカウンセラーの配置が進められています。
日本では,死別や悲嘆はしばしば私的な問題として捉えられがちで,感情の共有が難しい風土があります。そのため,悲嘆の過程が孤立の中で進行し,支援が届きにくいという課題もあります。死が日常に近づくとき,人は自らの生をどう意味づけるのか─その問いに対して,死生心理学はどのように応答し得るのか。留学中には,テロ事件も多く,対話を通して,悲しみを語ること,共有し合うことの重要性を再認識し,この一年の留学を通して,「喪の過程とは,他者との関係性のなかで自己を見つめ直す営みである」と実感するに至りました。喪とは,死者を思い,語り,そこに「私たち」というつながりを再発見する過程でもあります。制度の整備も重要ですが,やはり出発点は「人の心」にあると私は信じています。異なる価値観の交差に対して,互いに歩み寄りながらともに在る姿勢こそが,これからの社会に求められていくのではないでしょうか。
PDFをダウンロード
1