古典的実験機器はどのように使われていたか(4)─容積脈波測定装置の場合
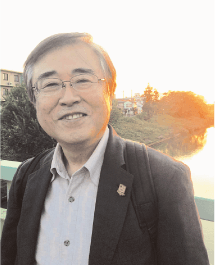
吉村浩一(よしむら ひろかず)
Profile─吉村浩一
京都大学大学院教育学研究科教育方法学専攻博士課程満期退学。京都大学教養部助手,金沢大学文学部講師,助教授,明星大学人文学部教授を経て,2003年より現職。専門は知覚・認知心理学。著書は『運動現象のタキソノミー』,『逆さめがねの左右学』(いずれもナカニシヤ出版)。




脈拍は,医学だけでなく,心理学においても感情変化に伴う身体反応指標として現在でも利用されています。古典機器の時代は,脈打つ腕のほんのわずかな体積変化を検出する方法で,脈動が記録されていました。写真1は『実験心理写真帖』(1910, 弘道館)に掲載されている容積脈波測定装置を使った実験の様子です。
被検者の右腕に装着されている「イ」が,容積脈波測定装置(plethysmograph)です。腕かすっぽり入る筒状の器具の中に体温と同じくらいの温水を満たし,上部にあけられた小さな煙突状の管にガラス管「ハ」を挿入し,ガラス管の中ほどまで温水を満たします。袖口などから水が漏れないようにしておくことが大切です。腕の血管が拡張するとき,ガラス管の水は押し上げられ,脈動に合わせて水がガラス管内で上下し,それを目視するのです。
水の上がり下がりを目で観察するだけならこれでよいのですが,研究用には脈動の時々刻々の変化をカイモグラフ(ル)に書かせる必要があります。それには,ガラス管上部にゴム管を差し込んで,「ニ」のタンブールにつなぎます。ガラス管内を水が上昇すればゴム管内の空気が圧縮されるのですが,その程度は微弱で,ペン先を動かしてカイモグラフに軌跡を描かせるパワーにはなりません。そこで,タンブールが必要になるわけです。タンブールの機能と現存品については本誌84号で解説済みなので詳しくは述べませんが,簡単に言うと,テコの原理などを利用して空気圧の微弱な変化を,ペンを動かす力に増幅する装置です。
容積脈波測定装置は,関西学院大学(KG00020)と東北大学(TH00046)に現存します。ともにドイツのZimmermann社製でLehmann式(開発者名)のものなので,ここには関西学院大学のものだけを示します(写真2)。ベルトを外すと台座から取り外せるようになっており,写真1では台座から取り外して使っています。下に敷かれたタオルはクッション代わりなのでしょうか。それならよいのですが,隙間から水が漏れることへの対応なら心配です。
関西学院大学には,このように上腕全体の容積を測定する容積脈波測定装置のほか,指だけを入れて測定するタイプのものも残っています。写真3に示したのがそれです(KG00007)。2013年8月に関西学院大学に残る古典的実験機器の調査にお邪魔したおりには,中島定彦教授と一緒に,名誉教授の宮田洋先生のお話をうかがいました。宮田先生は,ご自身の研究でこの器具を使われた生き証人で,その扱いの難しさについて想い出を語ってくださいました。
その内容は,宮田先生がお書きになった『人間の条件反射』(1965, 誠信書房)にも載っています。かいつまんで言うと,この器具には容器内に温水(38~39℃)を満たす水圧式と温水を入れない空圧式とがあるそうで,水圧式のものを長時間にわたって計測に用いるには,次のような難があったそうです。計器内に温水を循環させて一定温度に保つことが難しく,そもそも完全密閉することも難しく,また(血管の収縮ではなく)自発的な指の動きにより容積変化が生じてしまうなど,いくつもの難点があったそうです。写真3を見ると,タンブールに圧変化を送るガラス管口のほか,温水循環用の入り口や出口もあり構造が複雑です。安定した水圧を保つことの難しさが容易に想像できます。こうした難しさは,何も容積脈波測定装置に限ったことではなく,古典的実験機器全般に言えることで,適切に使うには,どの機器も日頃からの手入れと使う人の訓練が必要でした。
また,写真4に示したマーレー氏脈拍記器(TH00044,山越工作所製)や京都大学に残る脈拍記載器(KT00039,Zimmermann社製)のように,血管の脈動を物理的動きとして皮膚の上から感知してタンブールなどで増幅する方式のものも使われていました。
現在では,脈動の測定は非常に簡単に行えます。血液量の変化を皮膚表面に当てた光センサーを使って光の反射量や透過量の変化として電気的に読み取る光電式のもの(血液量が増えると,指や腕の内部の黒っぽさが増して光の透過量や反射量が減少します)や,腕に巻き付けたストレンゲージの伸び縮みによる電気抵抗値の変化として測定することができます。あとの時代から見ると,脈動を容積によって測定するという古典的方法は荒唐無稽のようにも思えます。しかし,明治,大正,それに昭和も戦前までは,重さ・体積・動きなど,考えうるものを総動員して,それらの変化を心や身体の状態変化として捉えていたのです。
PDFをダウンロード
1





